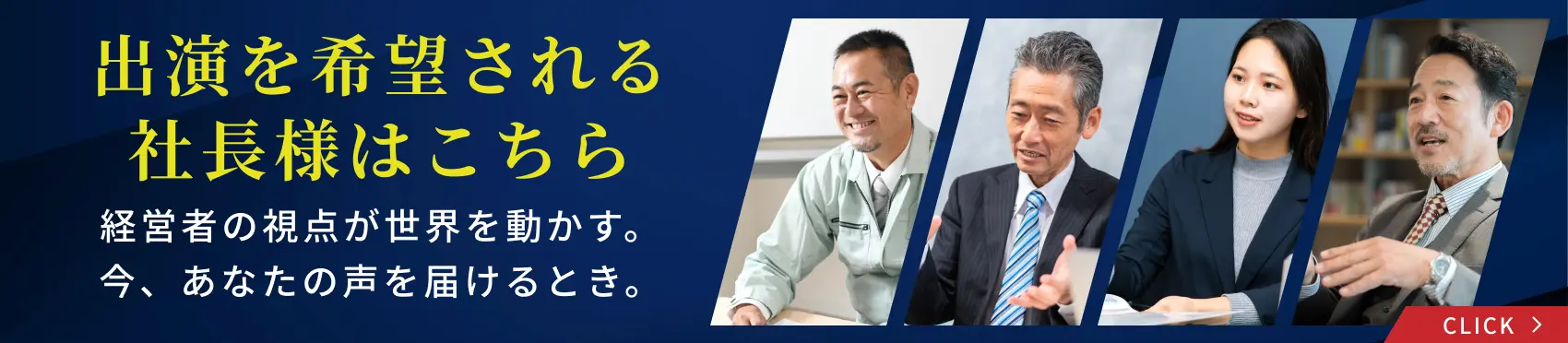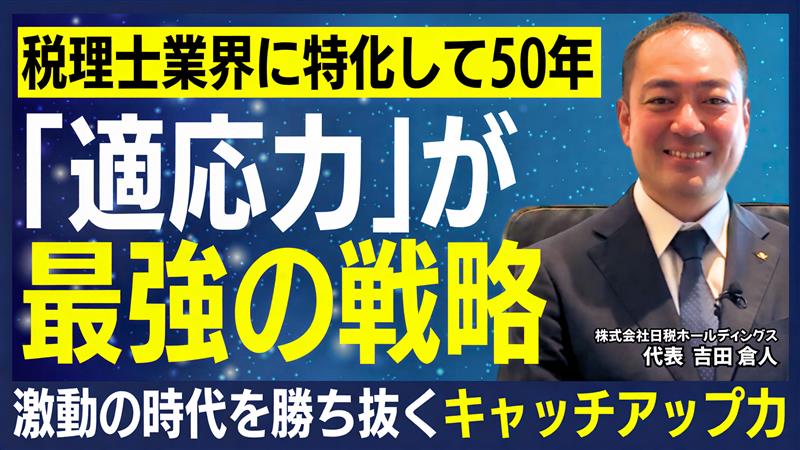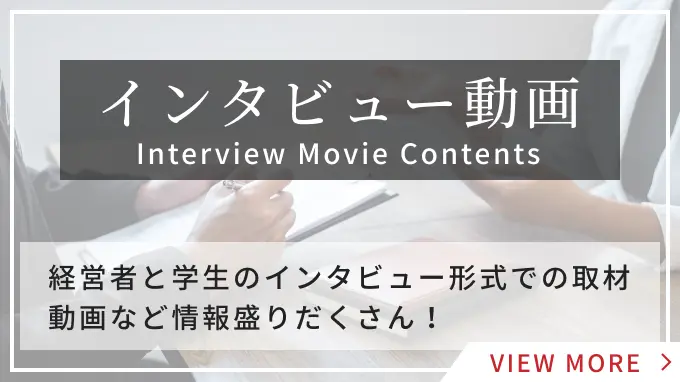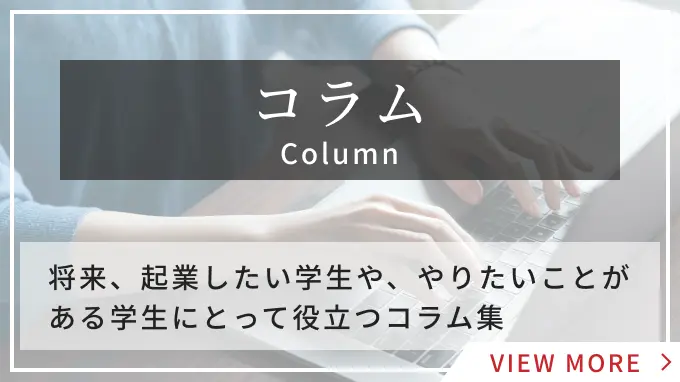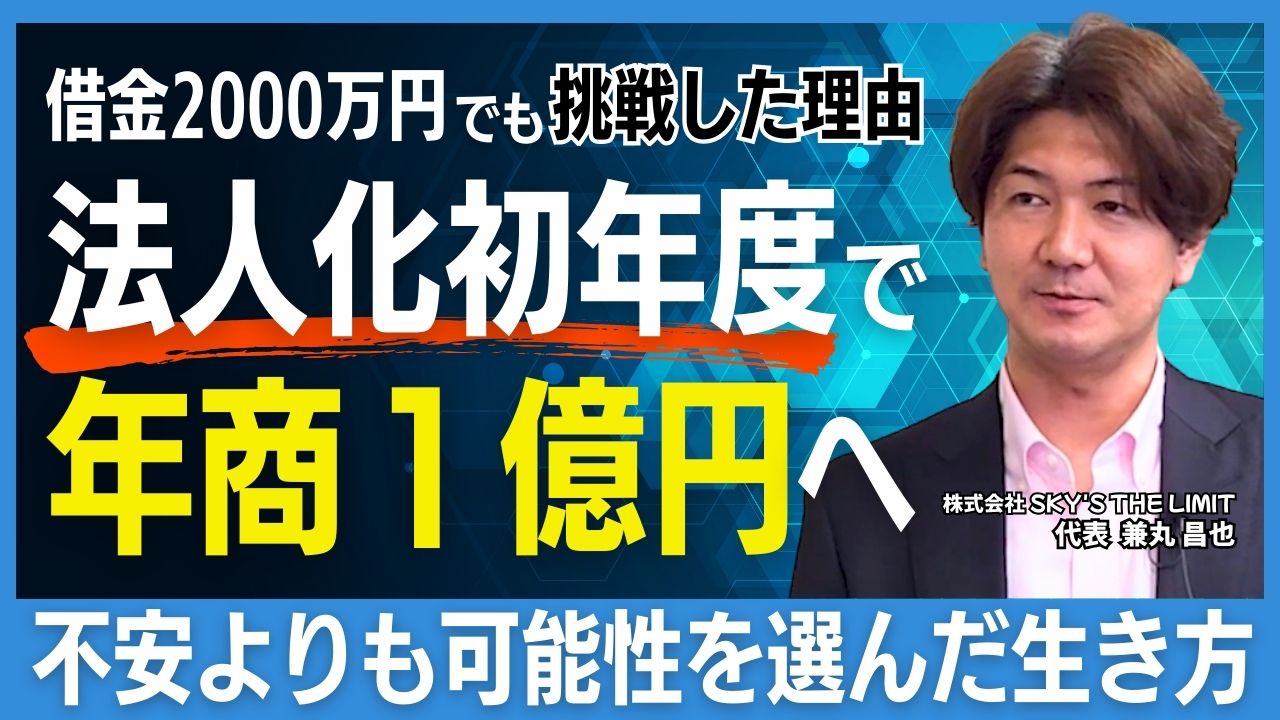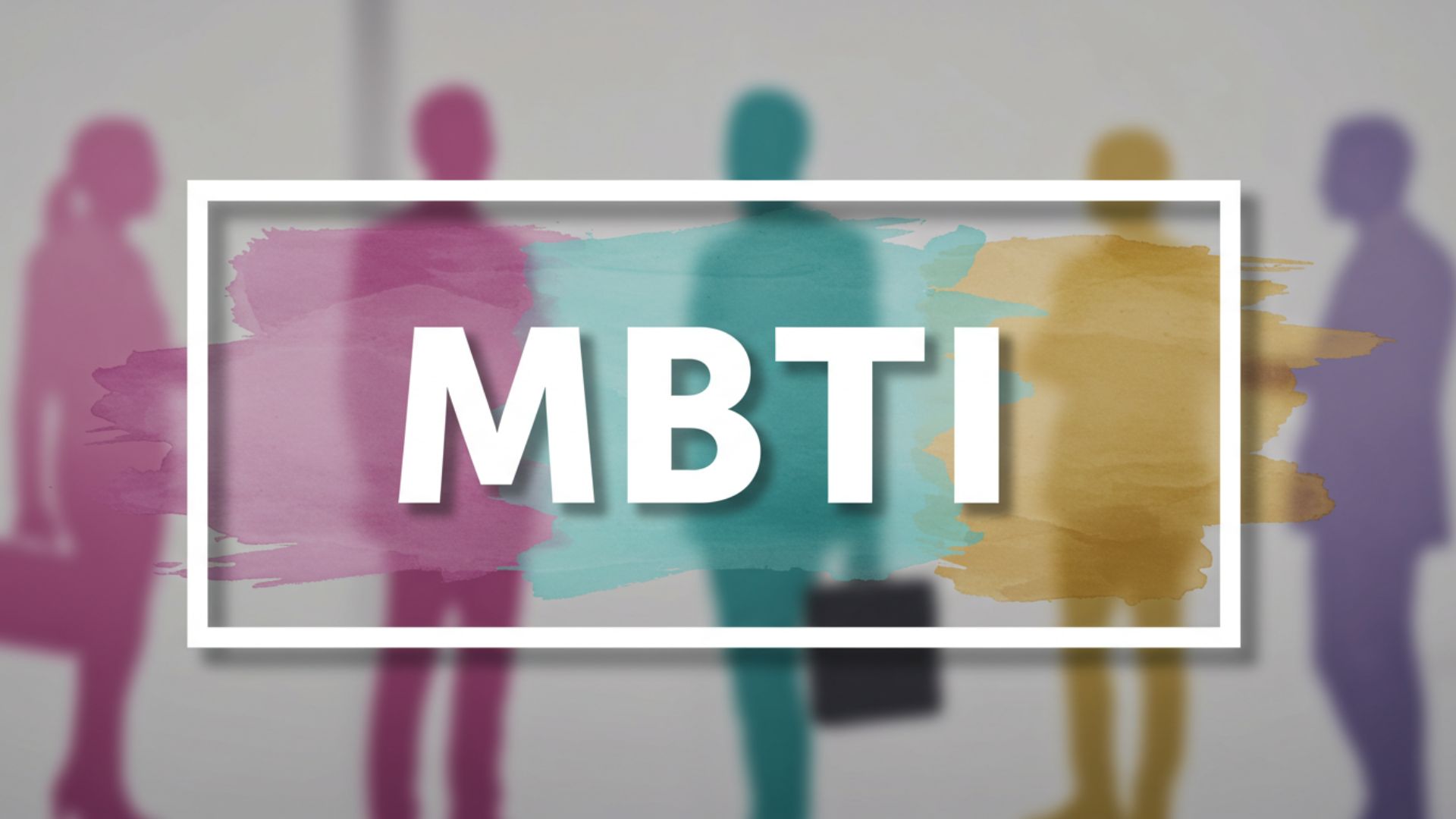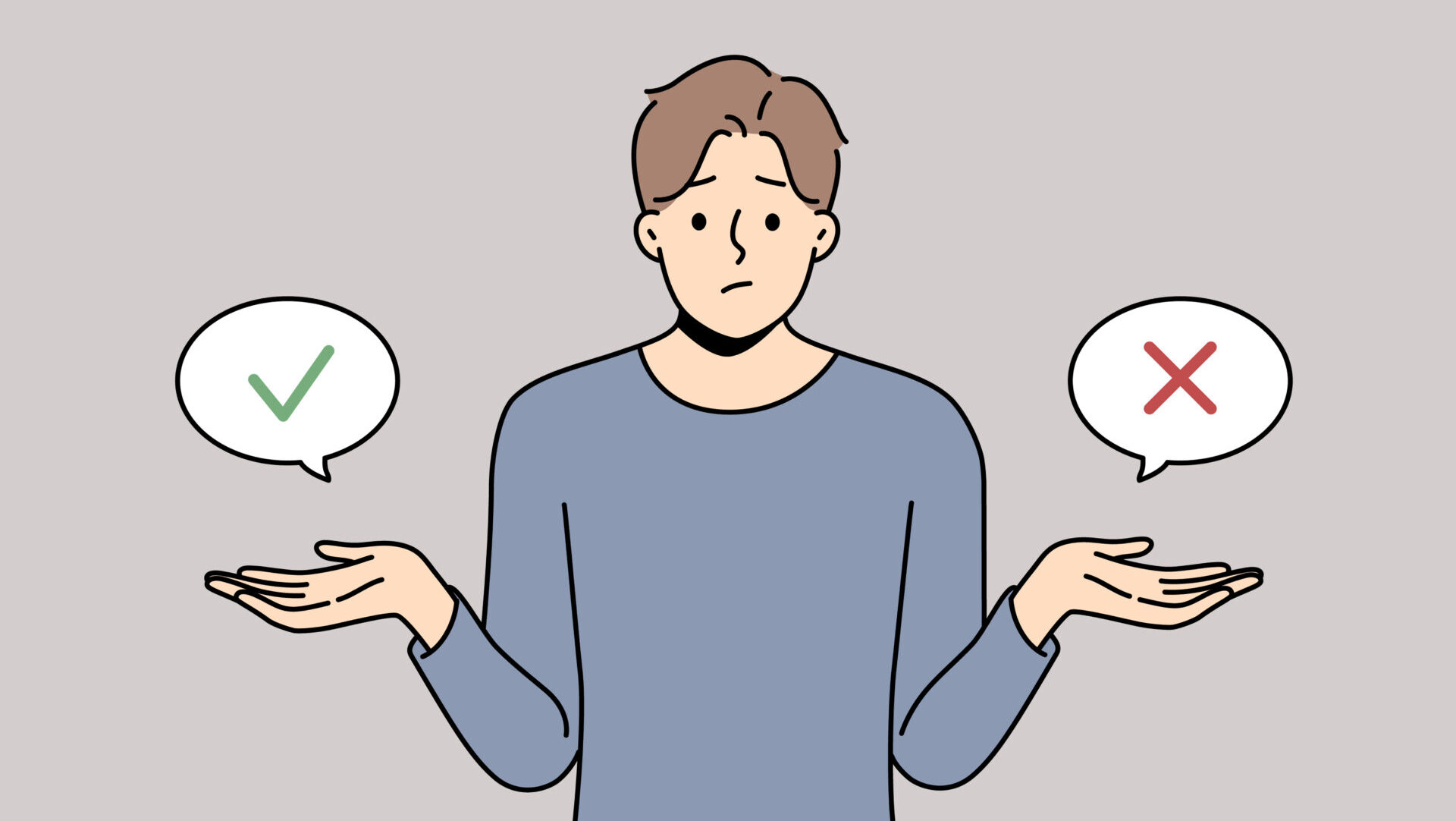「経営」と「運営」の違いとは?―ビジネスリーダーを目指す人の基礎知識

将来ビジネスの世界で活躍したいと考えている皆さんにとって、「経営」と「運営」という言葉は耳にする機会が多いのではないでしょうか。しかし、これらの言葉の具体的な意味や違いについて、明確に説明できる方は意外と少ないかもしれません。この記事では、多くの人が混同しがちな「経営」と「運営」の概念を明確にし、それぞれの役割や重要性を具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。この記事を読むことで、将来の起業や就職活動において、企業の戦略や日々の業務にどのように関わっていくべきか、実践的な視点が得られるでしょう。
学生が社長へ素朴な疑問を直接インタビュー!
起業のきっかけ、覚悟、そしてリアルな失敗談まで。社長の本音をチェック!
目次
「経営」と「運営」の違いを理解する

ビジネスの世界では、「経営」と「運営」という言葉がよく使われますが、これらの概念は混同されがちです。しかし、両者には明確な違いがあり、その理解はビジネスリーダーを目指す上で非常に重要になります。この章では、それぞれの言葉が持つ意味や目的、役割、そして視点の違いを掘り下げていきます。続くセクションで、それぞれの定義を詳しく見ていきましょう。
経営とは、企業や事業の全体的な戦略や方向性を決定する活動です。その主目的は収益化であり、事業が持続的に利益を生み出し、成長していくための土台を築くことにあります。例えば、どのような製品やサービスを開発し、どの市場に進出し、どのようなブランドイメージを構築するかといった、企業の未来像を描き、それを実現するための長期的な計画を立てることが経営の核となります。
具体的には、経営者は事業目的を達成するために、継続的かつ計画的に意思決定を行います。市場の動向、競合他社の状況、技術革新など、外部環境の変化を常に察知し、それに応じて組織や事業の体制そのものを構築したり、時には大胆に変更したりする権限を持ちます。これは、単に日々の業務を回すだけでなく、企業そのものの存在意義や進むべき道を定義し、変革をリードする役割を担っていると言えるでしょう。
経営の全体像(描く → 決める → 動かす → 伸ばす)
未来像を描く
市場・製品・ブランド
戦略を決める
長期計画・資源配分
組織を動かす
仕組み化・体制変更
利益・成長へ
持続的収益化
一方、運営とは、経営陣が定めた戦略や方針に基づき、日々の業務を円滑かつ効率的に遂行するための具体的な活動を指します。運営の主目的は効率化であり、限られた資源の中で最大の成果を出すことを目指します。例えば、生産ラインの最適化、顧客対応のフロー改善、従業員のシフト管理などが運営の具体的なタスクに当たります。
運営者は、与えられた体制の中で、いかに生産性を高め、目標を達成するかに注力します。組織をまとめ、滞りなく動かすための短期的な視点に立った活動が中心です。日々の業務がスムーズに進むように、計画を立て、実行し、進捗を管理し、問題が発生すれば速やかに解決策を見つけます。つまり、運営は、経営が描いたビジョンを実現するための現場での実行力そのものと言えるでしょう。
運営の全体像(計画 → 実行 → 管理 → 改善)
計画を立てる
シフト管理・業務設計
実行する
生産ライン・顧客対応
進捗を管理
効率・生産性チェック
問題を改善
トラブル解決・最適化
ここまで見てきたように、「経営」と「運営」は異なる目的と役割を持っています。簡単に整理すると、経営は企業の頭脳であり、全体像を描き、方向性を定める役割を担います。一方、運営は企業の手足であり、頭脳が定めた方向に従って具体的に動く役割を果たします。経営の目的が収益化であるのに対し、運営の目的は効率化にあります。
時間軸で見ると、経営は長期的な視点で未来を描く活動ですが、運営は短期的な視点で日々の業務に焦点を当てます。また、視点においても、経営が全体戦略を重視するのに対し、運営は日常業務に特化します。経営者は組織や事業の体制そのものを作り変える権限を持ちますが、運営者は与えられた体制の中で最大限のパフォーマンスを引き出すことに注力します。
企業が安定し、成長していくためには、この経営と運営が互いに補完し合い、相互に機能することが不可欠です。どちらか一方が欠けても、企業は健全に発展することができません。例えば、どんなに素晴らしい経営戦略があっても、それを実行する運営力がなければ絵に描いた餅に終わりますし、日々の運営がどれほど効率的でも、明確な経営戦略がなければ企業は方向性を見失ってしまいます。
経営と運営の比較
🧠 経営(頭脳)
- 目的:収益化(全体で利益を生み続ける)
- 役割:全体像を描き、方向性や戦略を定める
- 時間軸:長期視点で未来を描く
- 権限:組織や体制そのものを設計・変更できる
- 指標例:売上成長率/市場シェア/ブランド価値
🛠️ 運営(手足)
- 目的:効率化(限られた資源で成果を最大化)
- 役割:方針に基づき現場を動かす
- 時間軸:短期視点で日々の業務に集中
- 権限:与えられた体制内で成果を最大化
- 指標例:稼働率/リードタイム/顧客満足度
企業や店舗における「経営」と「運営」の実践例

これまでの章では、「経営」と「運営」の基本的な概念について深く掘り下げてきました。ここからは、理論的な理解をさらに深めるために、実際のビジネス現場でこれらがどのように実践されているのかを具体的に見ていきましょう。企業全体での「経営」のあり方や、より身近な店舗での「運営」の事例を通して、皆さんの学習が実践的な知識へと繋がるよう、具体的なシナリオを交えながら解説していきます。
会社経営における経営は、企業の存続と成長を左右する最も重要な活動です。企業のトップである経営者は、常に変化する市場の動向を正確に分析し、競合他社の戦略を把握しながら、自社が将来的にどのような姿を目指すのか、その事業の全体像を描きます。例えば、新しい技術トレンドを見極めて新規事業への参入を決定したり、既存事業の多角化戦略を策定したりするのも経営判断の一つです。
そして、描いた事業の将来像を実現するためには、適切な資金調達が不可欠です。銀行からの融資や投資家からの出資を募る財務戦略、また、事業を推進するための組織体制をどのように構築し、優秀な人材をどこから採用するかといった組織戦略も、経営者の重要な役割です。これらの戦略的な意思決定は、常に企業の収益化という目的を意識して行われます。
会社経営を成功させるためには、社員が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、働きやすい環境を整えることも非常に重要です。また、経営ノウハウは常に進化しているため、書籍やセミナーなどを通じて継続的に学習し、自社の経営に積極的に取り入れる姿勢が求められます。
一方で、組織のトップが日々の業務を効率的にこなす運営者意識に留まってしまうと、企業は成長の機会を逃してしまうリスクがあります。市場の変化に対応できず、長期的な視点での戦略的な投資や変革が行われないことで、競合に遅れをとり、最終的にはビジネスの失敗につながる可能性も出てきます。だからこそ、経営者には常に先を見据え、全体を俯瞰する経営者意識が不可欠なのです。
店舗運営は、設定された経営戦略のもとで、日々の業務をいかに効率的かつ効果的に回していくかに焦点を当てた活動です。例えば、フランチャイズの店舗を任されている、雇われ店長は、本社の定める経営方針や売上目標に基づいて、具体的な運営計画を立てます。これには、スタッフのシフトを最適化して人件費を抑制しつつサービス品質を維持することや、商品の在庫を適切に管理して廃棄ロスを減らすこと、そしてお客様に満足いただける接客サービスを提供し、リピーターを増やすための工夫などが含まれます。
店舗運営を成功させるためには、まず明確な目標をチーム全体で共有することが大切です。「今月の売上目標は○○円、そのために来店客数を△△人増やす」といった具体的な数値を掲げ、スタッフ一人ひとりがその目標達成に貢献できるよう意識を高めます。また、スタッフが安心して働けるストレスの少ない職場環境を整備することも、運営の効率化には欠かせません。良好な人間関係や適切な休憩時間の確保は、スタッフのモチベーションを高め、生産性向上に直結します。
ここで、経営の視点を持つ店長と比較してみましょう。例えば、個人経営の飲食店でオーナー兼店長を務める人は、日々の運営業務に加えて、利益を最大化するために新しいメニューの開発、原価率の計算、価格設定の変更、さらには近隣の競合店の分析まで多角的に行います。これは、店舗全体の売上を伸ばし、利益を確保するための経営判断です。一方、雇われ店長は、提供されたメニューや価格体系の中で、いかに効率よくお客様にサービスを提供し、本社の指示に従って売上目標を達成するか、という運営に注力する傾向があります。
店舗運営の本質
🎯 目的
効率化(限られた資源で成果最大化)
⚙️ 方法
シフト最適化・在庫管理・接客改善
🤝 成功の鍵
目標共有と働きやすい環境
📈 本質
日々の改善の積み重ねが成果に直結
このように、店舗運営では、与えられた資源と目標の中で、いかに「効率化」を実現するかが重要なポイントとなります。日々の細やかな業務改善の積み重ねが、店舗の成功に大きく貢献するのです。
「経営」と「運営」は、それぞれ異なる役割を持っていますが、これらは決して独立したものではなく、企業の安定と成長のためには密接に連携し、互いを補完し合う関係にあります。会社経営が全体の方向性を定め、店舗運営がそれを現場で具体的に実行することで、企業は一つの目標に向かって力強く進むことができるのです。
例えば、本社の経営陣が「来期の売上を30%増やす」という戦略(経営)を立てたとします。この目標を達成するために、各店舗の運営責任者(店長など)は、具体的な販売キャンペーンの企画・実行や、来店客数を増やすための地域密着型イベントの実施といった運営レベルの戦術を練ります。さらに、現場で得られたお客様の声や売上データ、スタッフの意見といった情報は、フィードバックとして本社に送られます。
本社はこの現場からのフィードバックを受けて、当初の経営戦略を微修正したり、新たな商品開発のヒントを得たりします。このように、経営層が立てた戦略が現場で実行され、その結果が再び経営層に還元されるという相互作用が繰り返されることで、企業は外部環境の変化に柔軟に対応し、持続的な成長を実現することができるのです。
経営と運営を成功させるためのポイント

これまで、「経営」と「運営」それぞれの役割や違いについて理解を深めてきました。ここでは、この二つの要素をビジネスで効果的に機能させ、成功へと導くための普遍的なポイントについてお話しします。長期的な戦略的な視点と、それを実現するための日々の実行力を兼ね備えることが、企業の持続的な成長には不可欠です。
組織全体が同じ方向を向いて進むためには、目標を明確に設定し、それを組織全体で共有することが非常に重要です。たとえば、経営レベルでは「5年以内に業界シェアNo.1を獲得する」といった、企業全体の進むべき方向性を示す長期的でビジョナリーな目標が設定されます。
一方、運営レベルでは、この大きな目標を達成するために「今四半期の新規顧客獲得数を10%増やす」といった、より具体的で測定可能な目標に分解されます。これらの目標は、単にトップダウンで指示されるだけでなく、全社員にその意義が共有され、納得感を持って受け入れられるプロセスが不可欠です。
目標が明確に共有されることで、社員一人ひとりが自分の業務が組織全体の目標達成にどう貢献しているかを理解し、主体的に行動するモチベーションが生まれます。これにより、組織全体の実行力は飛躍的に高まり、効率的な運営と経営目標の達成につながっていくのです。
長期的な戦略である「経営」と、短期的な効率化を追求する「運営」は、時に相反するように見えますが、両方をうまく両立させることが成功の鍵となります。たとえば、日々の業務効率化ばかりに注力しすぎると、市場や顧客の変化を見落とし、長期的な成長戦略を見失うリスクがあります。
逆に、壮大な戦略ばかりを練っていても、現場での具体的な実行力が伴わなければ、その戦略は絵に描いた餅で終わってしまいます。このような状況を避けるためには、経営層と現場が定期的に情報交換を行い、市場や顧客からのフィードバック、運営データに基づいて戦略を柔軟に修正していく必要があります。
また、全従業員が自分たちの会社を良くしていくという当事者意識、つまり経営者意識を持つことが両立の鍵です。現場で得られた知見が戦略に反映され、戦略が現場の効率化を後押しするような好循環が生まれることで、企業は持続的な成長を実現できるのです。
これまで学んだ「経営」と「運営」の知識を、ご自身のキャリアにどう活かしていくかを考えることが重要です。まずは、ご自身が将来的にどちらの領域に興味があるのか、あるいは両方のスキルをどのように身につけていきたいのかを具体的に考えてみましょう。
経営スキルを磨くためには、企業の有価証券報告書や決算資料を読み解き、その企業の経営戦略を分析してみるのがおすすめです。また、ビジネスコンテストに参加して、自ら事業計画を立案し、その実現可能性を追求することも貴重な経験となるでしょう。一方、運営スキルを高めるには、大学のサークル活動やアルバイト先でリーダーシップを発揮し、業務フローの改善を提案してみるのが効果的です。インターンシップに参加して、実際の現場でオペレーションやチームマネジメントを学ぶことも、具体的な運営ノウハウを習得する良い機会になります。
このように、座学だけでなく実践を通じて、ご自身の興味や適性に合わせて具体的なアクションを起こすことで、将来のビジネスリーダーとしての基礎を確実に築いていくことができるはずです。
まとめ:ビジネスリーダーとしての成長を目指して

この章では、ビジネスリーダーとしての成長を目指す皆さんに向け、これまで解説してきた「経営」と「運営」の本質を改めて振り返り、次のステップへと繋がる重要なポイントを整理していきます。
企業の成長にとって、「経営」と「運営」の両方が適切に機能することが不可欠です。未来のビジョンを描き、戦略を立案する「経営」がなければ、企業は進むべき方向を見失ってしまいます。一方で、その戦略を日々の業務に落とし込み、着実に実行する「運営」が伴わなければ、どんなに素晴らしい戦略も絵に描いた餅で終わってしまいます。
したがって、企業が持続的に成長するためには、この二つの機能が常に連携し、バランスを保つことが非常に重要です。どちらか一方に偏ってしまうと、例えば戦略ばかりで現場が疲弊したり、目の前の業務に追われて変化への対応が遅れたりといった問題が生じ、企業の成長は滞ってしまいます。
まとめ|経営=長期×収益化 / 運営=短期×効率化
経営(企業の頭脳)
- ビジョン・方向性の提示
- 事業戦略/資金調達/組織設計
- 長期視点で収益化を設計
- 体制そのものを創る・変える
運営(企業の手足)
- 業務フロー最適化・標準化
- シフト/在庫/CSの改善
- 短期視点で効率化し成果最大化
- 与えられた体制でパフォーマンス
- 企業評価は「経営戦略⇄運営体制」の連携度で見る
- 自分はどちらのスキルを伸ばすか——今月の行動を1つ決める
経営と運営がバランス良く機能することで、企業は安定し、持続的な成長を実現できます。経営層が市場の変化を捉えて新たな戦略を打ち出し、それを運営部門が具体的なアクションとして実行する。そして、現場で得られた情報や課題を経営層にフィードバックし、戦略を微調整するといったサイクルが回ることで、外部環境の変化に強いしなやかな組織が生まれます。
また、全従業員が自社の経営理念やビジョンを理解し、日々の運営業務がその実現にどう貢献しているかを認識することで、仕事へのモチベーションが高まります。このように、経営と運営が一体となって機能する企業文化を築くことが、組織の安定と成長の礎となるのです。
この記事を通じて「経営」と「運営」の違いや重要性を理解した皆さんは、ぜひ次のステップへ踏み出してください。例えば、インターンシップや就職活動で企業を選ぶ際には、その企業の経営戦略と、現場の運営がどのように連携しているのか、という視点から分析してみましょう。企業の採用担当者に、具体的な事業戦略とそれを実行する現場の体制について質問してみるのも良い経験になります。
また、ご自身のキャリアを考える上でも、経営的な視点に興味があるのか、それとも現場での運営を効率化することにやりがいを感じるのか、あるいは両方のスキルをバランス良く身につけていきたいのか、といった問いを自分自身に投げかけてみてください。今日学んだ知識が、皆さんの将来のキャリアパスを考える上で、きっと具体的な行動を促すきっかけになることでしょう。

経営コンサルタント
[中小企業診断士] [社会保険労務士]
20年以上にわたり燃料業界を中心とした中小企業のDX推進を支援。
現在は製造業・小売業・サービス業など幅広い分野に対して、
IT活用や業務効率化、経営戦略の策定などを一貫してサポート。
講演やセミナーにも登壇し経営や起業の実践的なアドバイスを得意とする。
最新記事