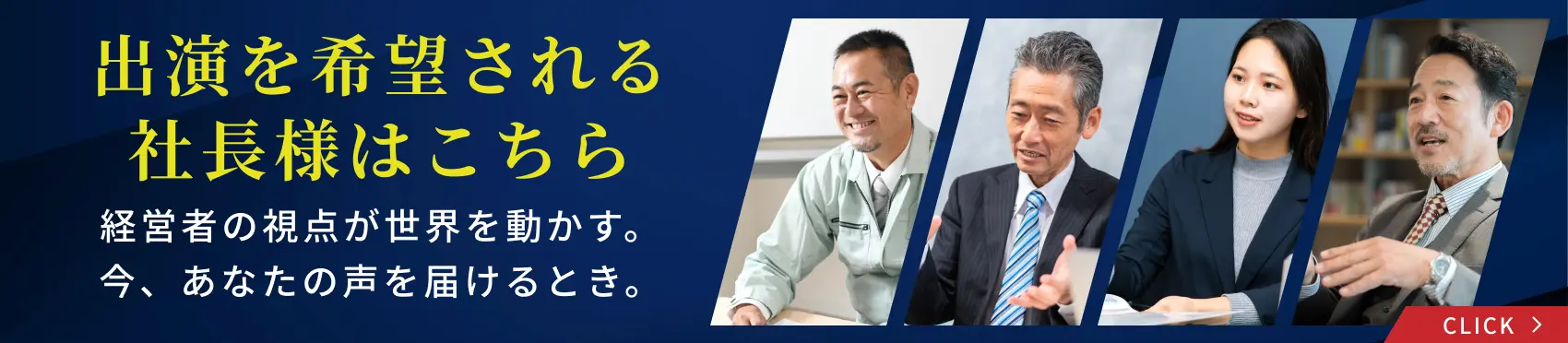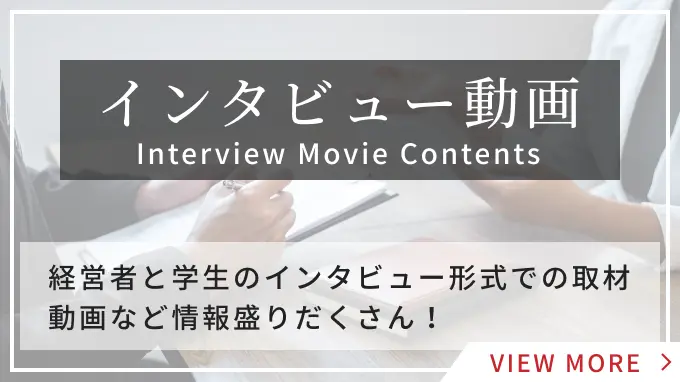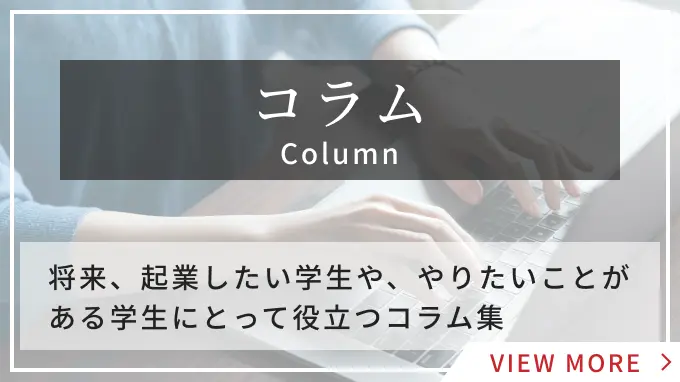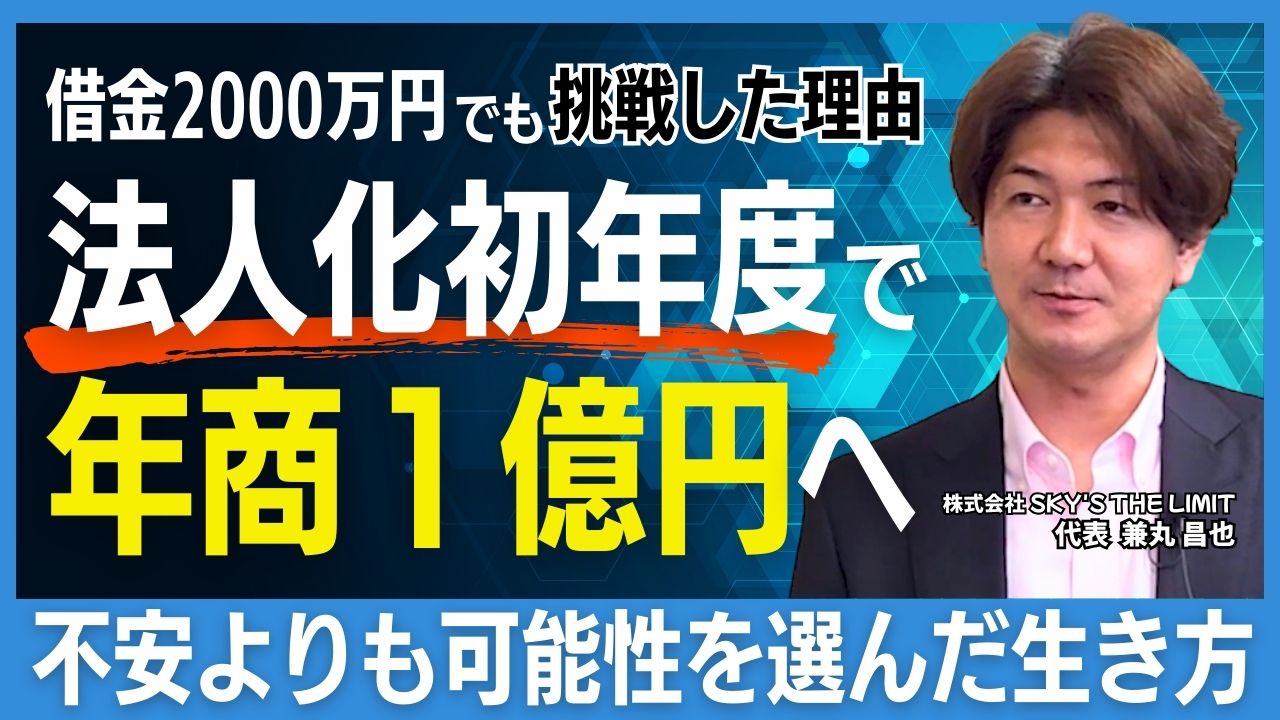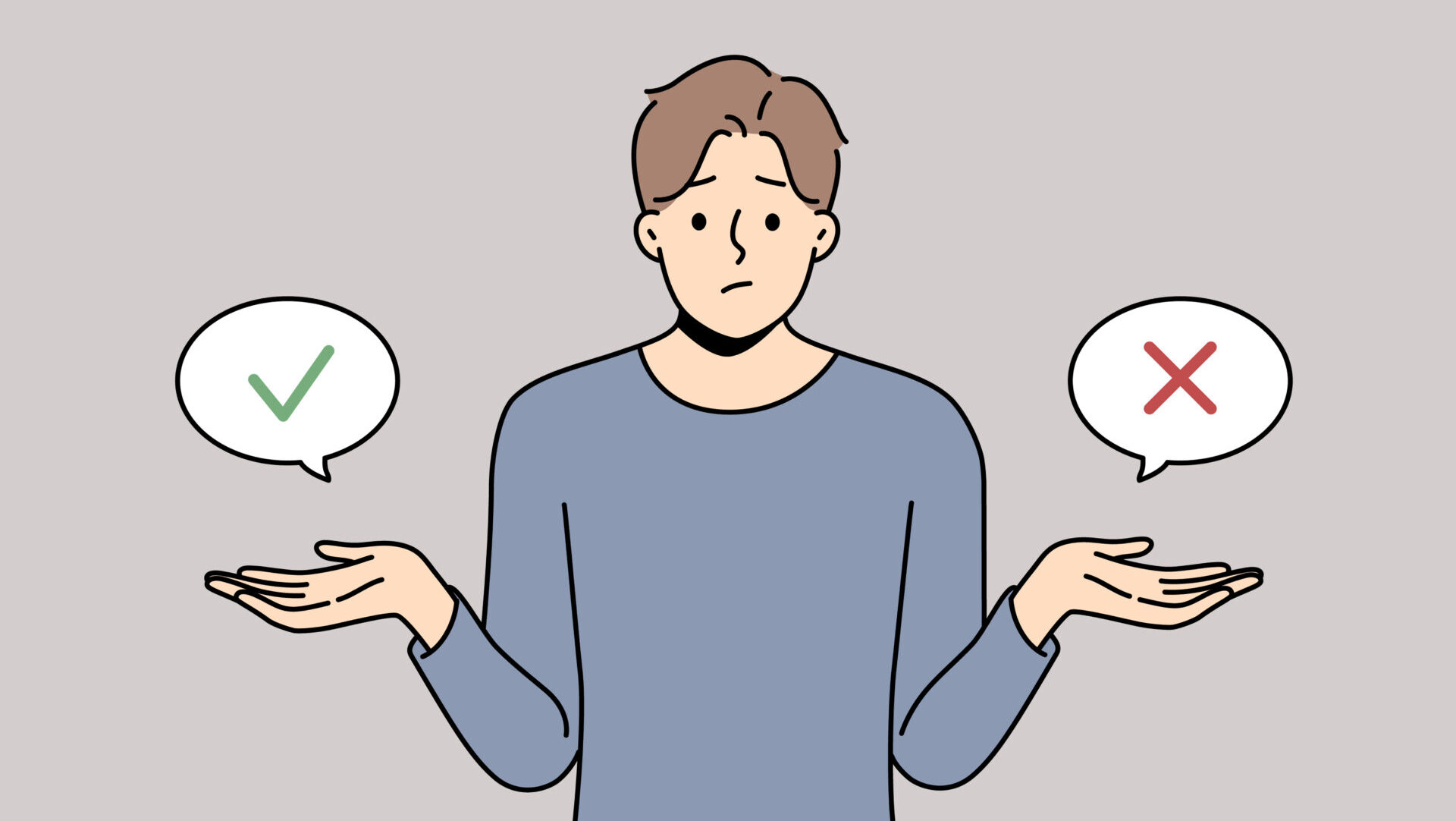【MBTI診断】経営者に向いている性格タイプ top5を徹底解説!
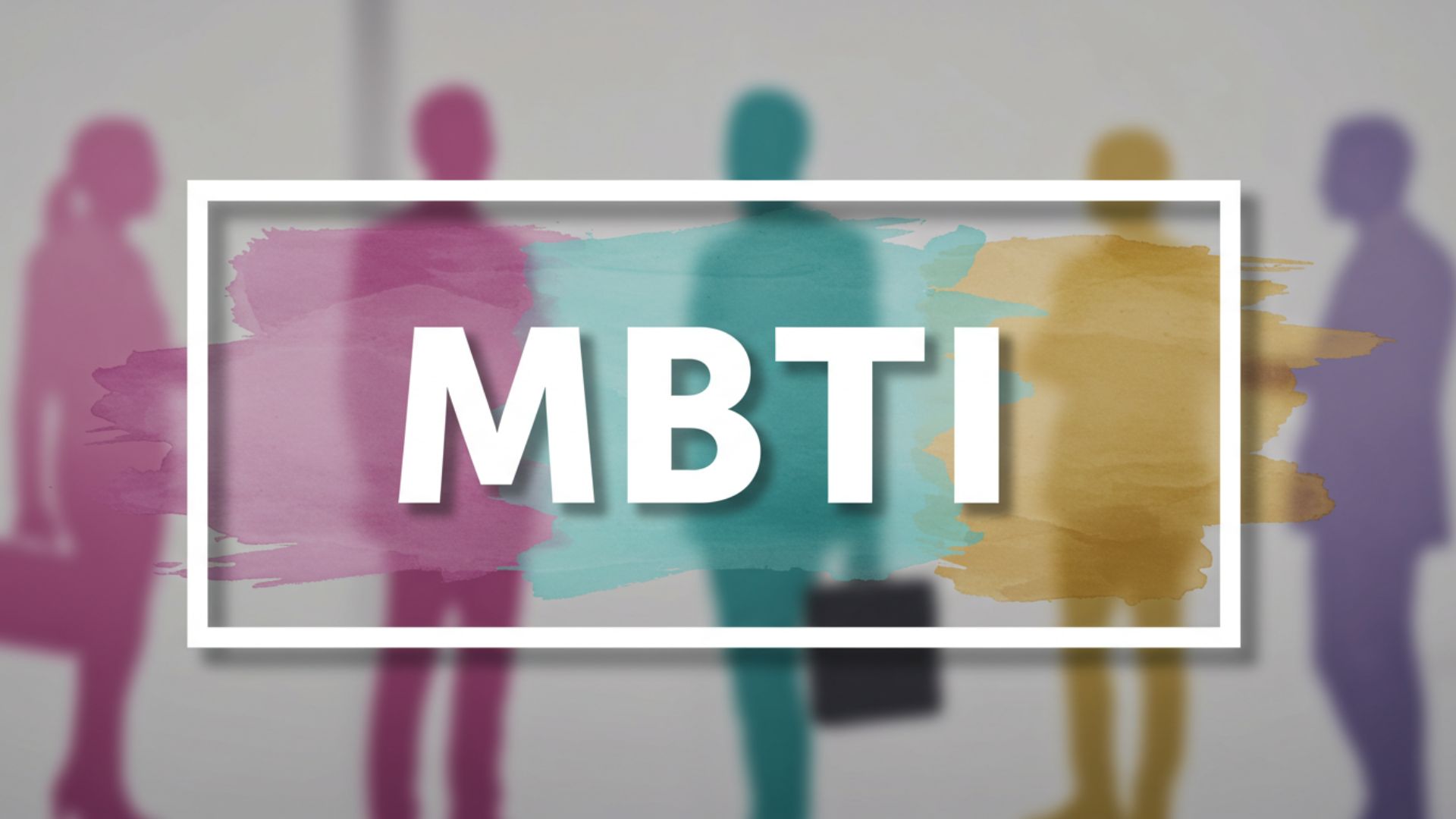
MBTI診断とは?性格タイプを知る重要性

MBTI診断が生まれたのは第二次世界大戦の混乱期です。当時、米国では軍需工場へ大量の女性が動員され、短期間で適材適所を判断できるツールが求められていました。主婦だったキャサリン・クック・ブリッグスは娘のイザベル・ブリッグス・マイヤーズと協力し、心理学者カール・グスタフ・ユングのタイプ論を実用レベルに落とし込む形で質問紙を開発しました。ユングが提唱した外向‐内向や思考‐感情などの概念をベースにしつつ、「誰もが自分らしく働ける環境を作る」という母娘のビジョンが加わり、その開発は1940年代から進められ、初期の質問紙が作成されました。そして、現在のMBTIの基礎となる包括的なアセスメントとして広く知られるようになったのは、1962年の正式な出版以降です。
診断の軸は4つあり、それぞれが二分法で成り立っています。外向(E)か内向(I)かはエネルギーの充電方法を示し、たとえば会議後にさらに雑談をして元気になる人はE、静かな環境で一息つく人はIに該当しやすいです。感覚(S)か直観(N)は情報の取り込み方を示し、Sタイプはデータや経験を重視し、Nタイプはアイデアや可能性に目を向けます。思考(T)か感情(F)は判断基準を示し、Tは論理や一貫性を、Fは人間関係や価値観を優先します。最後の判断(J)か知覚(P)は行動スタイルを示し、Jは計画通りに進めるのを好み、Pは状況に合わせて柔軟に動くことを好みます。この4軸を組み合わせると2×2×2×2=16タイプとなり、例えばENTJは外向・直観・思考・判断が強いリーダー型として知られます。
現在、MBTIは世界50か国以上で年間500万人以上が受検すると言われ、国際的な人材開発ツールとして定着しています。適性把握とコミュニケーション改善を兼ね備えた診断として、組織規模を問わずニーズが広がっているのが現状です。
一方で、学術界からは「同じ人が再受検するとタイプが変わる割合がある」「16タイプが性格の全てを説明できるわけではない」などの批判も存在します。また、その統計学的妥当性や信頼性については、学術界から疑問が呈されている点も事実です。実務で活用する際は、診断結果を絶対視せず傾向を示す参考データとして扱う、他のアセスメント(360度評価や能力テスト)と組み合わせる、といった留意点が欠かせません。限界を理解したうえで使いこなせば、MBTIは自己理解とチームづくりを加速させる有力なコンパスとして機能します。
高額な判断を伴うM&Aや新規事業投資は、経営者の性格特性に大きく影響されることがあります。MBTIを通じて自身のタイプを理解することで、「短期成果へ傾きやすい」や「感情を優先しがち」といった潜在的なバイアスを事前に認識し、リスクマネジメントや意思決定フローに補正項目を組み込むことが可能になります。これにより、予期せぬ問題(ヒヤリ・ハット)を減らし、戦略の精度を高めることにつながります。
タイプ間の相互補完も重要 です。例えば、ビジョナリーなタイプであるENTJのCEOと、実務的で詳細を重視するISTJのCFOが連携することで、将来の展望と具体的な数値管理のバランスが自然に取れる可能性があります。また、MBTIのタイプ特性を考慮したチーム編成や個人の働き方の調整は、社員エンゲージメントの向上や創造性の促進に寄与するとされています。例えば、内向型(I)の人が一人で集中して戦略を練る時間を確保したり、外向型(E)の人が日常的にブレインストーミングを行う機会を設けることで、個人の自律性や関係性のニーズが満たされ、結果として職場の満足度や生産性の向上に繋がったという報告もあります。
要するに、MBTIは「どのカードで勝負するか」を示す羅針盤です。強みを最大化し、弱点を補完する人材や制度を整えれば、経営スピードと組織の安定性を両立でき、複雑化する現代でも持続的な競争優位を築けます。
経営者に向いているMBTI性格タイプ top5

ESTPタイプは外向(E)、感覚(S)、思考(T)、知覚(P)の組み合わせによって、瞬時に状況を読み取り即断即決する力が際立ちます。
売上拡大フェーズでは、ESTPの社交性と論理的思考がネットワーキングと交渉術に結実します。スタートアップ初期のカオス環境を切り拓く行動力が際立ちます。分厚い事業計画よりも即時実行を選び、数時間でプロトタイプを公開するスピードは市場投入のタイミングを逃しません。外向性と知覚型の組み合わせが、顧客の反応をリアルタイムで読み取る柔軟性を生み、商談成立率やリードタイム短縮といったKPIに直結しやすい点が大きな魅力です。
一方でESTPは長期的ビジョンの設計や細部の管理を後回しにしがちです。この弱点を補完するには、CFO型パートナーや週次KPIレビューによるガバナンス体制を構築し、OKRで目標と進捗を数値化する仕組みが有効です。これにより「行動力」と「統制力」のハイブリッドが実現し、スピードを維持したまま持続可能な経営が可能になります。
ESTP経営者が持続的成長を遂げるコツは「感覚的決断+データドリブン管理」のハイブリッド化です。クラウドBIツールを導入し、MRR(毎月繰り返し収益)、NPS(顧客推奨度)、チーム生産性指数をダッシュボードでリアルタイム可視化すれば、直感と数字のズレを即座に補正できます。さらに、OKRを用いた四半期レビューや取締役との月次ディープダイブによって、短期的な判断が長期戦略と連動しているかどうかを定期的に確認することが重要です。これらの仕組みを整えることで、ESTP本来の行動力と柔軟性を保ちつつ、持続可能なスケールアップを実現できます。
ENTJタイプは、目標から逆算して全体像を組み立てる構造化思考の達人です。5カ年ビジネスプランを作成する際には以下のようなものがあります。
ENTJの段取り力が活きる5ステップ
- 10年後のパーパスを言語化:長期ビジョンを明文化
- PESTや5フォースで環境を数値化:外部要因を分析
- OKRで3〜5年の戦略目標設定:成果と指標を明確に
- 部門別リソースをCF計画に反映:財務的裏付けを構築
- 四半期マイルストーンを設定:進捗と調整を可能に
この段取り力が、組織全体を同じ北極星に向けて整列させる最大の武器になります。
一方で、命令口調になりがちなコミュニケーションは、大きな落とし穴となり得ます。「10倍成長」や「最速達成」など、アグレッシブな目標設定が常態化しやすく、その達成圧力が平均パフォーマーの士気を下げるリスクも高まります。OKRを四半期サイクルで運用し、進捗とビジョンの整合性を公開ダッシュボードで可視化することで、プレッシャーを透明性へ転換しやすくなります。さらに、成果と連動したスポットボーナスやピアボーナスを組み合わせることで、成果主義のメリットをチーム全体へ公平に波及させることが可能です。
プランを描くだけで終わらないのもENTJらしさです。達成度を見える化するためには、KPIを財務・顧客・プロセス・学習の4視点でリスト化し、ダッシュボードにリアルタイム表示する方法が有効です。例えばARR、NPS、開発サイクルタイム、ナレッジ共有回数を週次でレビューし、達成率80%未満の項目は即座に改善タスクへリレー。PDCAサイクルを月1回の全社ミーティングで回し、「Planは数字、Doは担当者、Checkはダッシュボード、Actはリソース再配分」というフォーマットに固定すると、戦略と現場が噛み合ったまま高速で前進できます。
ESTJタイプは「外向(E)・感覚(S)・思考(T)・判断(J)」の組み合わせにより、事実ベースの判断と厳格なプロセス管理を得意とします。財務・人事・法務といった組織の基幹部門を横断的に統括する場面では、数字に裏打ちされた現実主義と、決めた手順を徹底する規律重視の姿勢が大きな武器になります。たとえば資金繰りにおいては、キャッシュフロー計算書を週次でレビューし異常値を即座に是正、同時に人事部門へ採用計画の見直しを指示するなど、データドリブンで部門間を機敏に連携させる能力に長けています。
コンプライアンスの観点でもESTJの強みは顕著です。ISO 9001(品質マネジメント)やISO 27001(情報セキュリティ)を取得するプロジェクトでは、「現状ギャップ分析→是正計画立案→手順書作成→内部監査→外部審査」という5ステップを厳密に管理し、期限遵守率を95%以上に保つ傾向があります。さらに上場企業ではJ-SOX対応として、財務報告の信頼性を担保する内部統制システムを構築する必要がありますが、ESTJ型リーダーは「業務記述書の棚卸し→リスク評価→統制活動の設計→テスト計画→モニタリング」というPDCAをテンプレート化し、部門別にKRI(Key Risk Indicator)を設定することで、監査法人からの指摘件数を大幅に削減するといった成果に繋がりやすいと考えられます。
一方でESTJはルールや既存プロセスを重視するあまり、急激な市場変化に適応しづらいリスクを抱えます。手順を守る意識が強すぎると、市場の変動や技術革新への対応が遅れ、チームの創造性を抑圧してしまうおそれがあります。ESTJリーダーは、スプリントレビューやカンバンボードといった可視化ツールを通じてルールを再定義することで、変化への抵抗感を最小化しながら柔軟性を取り込むことができます。
組織文化と業績を同時に高める管理型リーダーシップを実践するには、以下の 5つのアクションが効果的です。
管理型リーダーシップを実践する5つのアクション
- 週次で「マネジメントダッシュボード」を閲覧:財務・人事・法務の指標を統合し、リスクを早期発見
- 年1回、全社業務プロセスを棚卸し:重複や陳腐化を可視化し、無駄を省く
- OKRによる目標管理制度を導入:部門と個人の目標を連動させ、成果を最大化
- 改善提案制度を整備:現場から月10件以上のフィードバックを収集し、継続改善を促進
- 四半期ごとにタスクフォースを編成:部門横断チームでイノベーションテーマを検討
これらを取り入れることで、ESTJの規律性を維持しつつ変化への適応力も養え、翌日からでも具体的な改善に着手できます。
ENFJタイプは、相手の感情を瞬時に読み取る共感力と未来を鮮やかに描写するビジョン提示力を併せ持ちます。これら二つの資質が掛け合わさると、ストーリーテリングによる社員コミットメント向上が実現します。たとえば全社キックオフの場で「私たちの事業は10年後、まだ見ぬ顧客の人生をどう変えているか」を物語形式で語りながら、具体的な数値目標やロードマップを組み込むことで、社員は自分ごととしてビジョンを受け取ります。心理学では物語構造が感情移入を促進し、行動意図を高める「ナラティブ・トランスポート効果」が知られていますが、ENFJはこの効果を自然に引き出せる数少ないタイプです。結果として、360度サーベイでの「会社の目的に共感している」という項目のスコアが前年より15ポイント上昇するといったケースが珍しくありません。
社会的使命感を事業戦略に織り込む力もENFJの真骨頂です。ビジョンを語るだけでなく社会実装までやり切ることで、ENFJは理念と収益の双方を拡大させることに成功します。
一方で、対人感情に敏感すぎるがゆえの課題も存在します。部下の表情が曇ると「何か問題があるのでは」と想像を巡らせ、意思決定を先送りしてしまう場面や、共感疲労(エンパシー・ファティーグ)からバーナウトに陥るリスクが高い点が代表例です。こうした弱点に対しては、メンタルヘルス指標を可視化するセルフケアアプリ(例:Insight Timer、AWARE)が有効です。さらに、週次リフレクションの時間をカレンダーに予約して思考整理を行い、情報と感情を分離したうえで「48時間ルール(意思決定は2日以内)」を設定すると、決断の遅れを防ぎつつ心身の負荷も抑えられます。加えて、心理的セーフティネットを構築する目的で、エグゼクティブコーチや産業医と定期的に面談する体制を整えると長期的なパフォーマンス維持に役立ちます。
近年、多くのENFJ経営者がデータドリブン経営への転換を図っています。感情と直感に頼りがちな点を補完するために、まずはBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、リアルタイムで主要KPIを確認できるダッシュボードを作成します。TableauやLookerといった可視化プラットフォームは、ストーリーテリングのスライドにも直接エクスポートできるため、ENFJのプレゼンスタイルと相性が抜群です。次に、データ分析に強いアナリティクス人材を経営企画部門に配置し、週次レポートの解釈を共同で行う仕組みを確立します。最後に、ABテスト文化を浸透させ「感覚ではなくファクトで語る」姿勢を組織全体へ波及させれば、ENFJ特有の情熱とデータの客観性が掛け合わさり、高速PDCAが回る企業体質が完成します。
ENTPタイプは、生まれつきの好奇心と論理的思考を組み合わせて、まるでアイデア製造機のように次々と着想を生み出します。特にブレインストーミングの代表的手法であるSCAMPER法(Substitute=代替、Combine=結合、Adapt=応用、Modify=変更、Put to other use=転用、Eliminate=削除、Reverse=逆転)との相性は抜群です。たとえばオンライン学習サービスを題材にすると、「Substitute」で講師をAI(人工知能)に置き換え、「Combine」でSNS型コミュニティを付加し、「Reverse」で受講者が講師にフィードバックする双方向モデルを構築する、といった具合に短時間で革新的ビジネスモデルを組み立てられます。ENTPの頭の中では、これら七つの視点が高速で組み替えられ、既存市場の隙間を突く独創的な提案が次々と生まれるのです。
一方で、ENTPの“討論好き”はチーム摩擦を生みやすいリスク要因です。議論が白熱しすぎてメンバーが萎縮し、アイデアが出なくなるケースも少なくありません。
アイデアを収益化する段階では、オペレーション面のギャップが顕在化しやすくなります。ここで鍵を握るのがCOO(Chief Operating Officer)の早期登用です。
具体的には、Objectiveを『12か月以内にユニットエコノミクスを黒字化する』と設定し、Key Resultに『CAC(顧客獲得コスト)を30%削減』『月次解約率を3%未満に抑制』など数値を明記。ENTPのアイデアがCOOのプロセス設計で実行力を得ることで、シリーズB調達前にEBITDA黒字を達成したスタートアップも存在します。創造性とオペレーションを橋渡しする仕組みを持てば、ENTPの強みは持続可能な利益へと変換されるのです。
MBTI診断を活用して経営者として成功する方法

タイプ別に最適な学習スタイルを取り入れることで、知識の吸収効率は大幅に向上します。
INTJは オンライン講座で体系的に深掘りするスタイルが適しており、ESFJは ワークショップで他者と議論しながら理解を深める形式が効果的です。
ENTPは実験しながら学ぶ プロトタイピング型、ESTPは現場で体験して覚える アクション型、ISFJは手順を積み上げていく 蓄積型の学習がフィットします。
経営リテラシーを習得するには、以下の3ステップで取り組むと無理なく継続できます。
1財務・マーケ・組織などの具体的な学習目標を設定する
2MBTIタイプに合った教材や手法を割り当てる
3週次で復習時間をブロックし、継続的に定着を図る
学習環境の構築もタイプ別に最適化できます。内省型のINFJやINTPはプロコーチとの1on1で深掘りし、外向型のENTJやENFJは経験豊富なメンターから即時フィードバックを受けると伸びやすいです。ENTPやENFPには刺激し合えるマスターマインドが適しています。導入時はゴールを明示し、候補者と相性確認を行い、期間・頻度・評価方法を合意書にまとめると関係が長続きします。
成長を可視化するにはデータ管理が不可欠です。四半期ごとに360度評価でリーダーシップ行動を数値化し、同時にOKRで売上やCAC削減などの定量KPIを設定します。エンゲージメントサーベイも併用し、ダッシュボードでリアルタイム監視すればPDCAサイクルが自動化され、改善点を即座に発見できます。
盲点を補うクロストレーニングも欠かせません。ENTPはGTDでタスクを細分化し実行ログを取り、ISTJはSCAMPERでプロセスを意図的に再構築、INFJはオンライン財務ケースで数値感覚を鍛えるとバランスが取れます。「得意を伸ばす学習」と「弱点を補う訓練」を並行させることで、経営者としての総合力が着実に底上げされます。
ホフステードの6次元モデル(権力距離・個人主義/集団主義・男性性/女性性・不確実性回避・長期志向・人生の楽しみ志向)は、MBTIタイプの行動様式に重ねて機能する「文化的フィルター」です。たとえば権力距離が低いスウェーデンでは、ENTJのトップダウン型リーダーシップが反発を招きやすいため、協働的プロセスを設計するほうが成果につながります。海外進出時は、現地文化が自分のタイプ傾向をどう修正するかを事前にシミュレーションし、意思決定のスピードやコミュニケーションのトーンを微調整することで、失敗確率を大幅に下げられます。同じESTPでも、シリコンバレーの「失敗歓迎」文化ではピボットを繰り返すCEO像が称賛される一方、100年企業の自動車メーカーでは安全第一の風土が即断即決をリスクと見なします。さらに、コロナ禍の国際調査ではリモートワーク下のバーンアウト率が外向型で高く、内向型で低いというデータも報告されています。したがって、外向型メンバーには週次オンライン懇親会を、内向型メンバーにはフレックスタイムや非同期コミュニケーションを提供するなど、タイプ別に環境変数を最適化することがマネジメントの要件になります。
文化的バイアスを越える具体策としては、年2回のダイバーシティ&インクルージョン研修で無意識バイアスを可視化し、プロジェクト開始時に文化チャーターを共同作成する方法が有効です。さらに「異文化×異タイプ」を意識したクロスカルチャルチームを組成し、月次でチャーターを振り返るガバナンスフレームを運用すれば、衝突がイノベーションへ転換しやすくなります。これらの体系的仕組みを継続すると、MBTI多様性と文化多様性の相乗効果が最大化され、組織全体のレジリエンスが高まります。
MBTI診断の限界と注意点

起業の成否は MBTI タイプだけでは語りきれません。多くの研究において、創業 5 年後に生き残った企業の成功要因として、創業者の過去の業界経験、コアメンバーとのネットワーク密度、資金調達タイミング、市場成長率など多様な要素が重回帰分析などにより有意であることが示されています。パーソナリティ(性格特性)は起業の成功に影響を与える重要な要素の一つですが、その具体的な寄与度を他の要因と比較して定量的に示すことは難しく、多くの要素が複雑に絡み合って成功に結びついています。つまり、成功は多因子の掛け算であり、MBTI はそのうちの 1 つのレンズにすぎないということです。
MBTI(イザベル・ブリッグス・マイヤーズらが開発した性格指標)は自己理解を深める優れたツールですが、心理測定学では再現性や妥当性への批判も存在します。例えば、別日程で同じ質問に回答するとタイプが変わる再テスト一致率は 50〜60% 程度とされ、ビッグファイブ(主要 5 因子性格検査)などより科学的に確立された性格検査と比較して、安定性が見劣りします。また MBTI は四つの指標を二分法で扱うため、連続的な個人差をざっくり分類しすぎるリスクがあります。人事配置や投資判断を MBTI だけに頼ると、適材適所を誤る可能性が高まります。
経営判断をより精緻に行うには、MBTI に加えて能力評価(コンピテンシー面接、ケーススタディ、数理テスト)、状況要因分析(PEST=政治・経済・社会・技術のマクロ環境、SWOT=自社の強み・弱み・機会・脅威)を組み合わせた総合アセスメントが有効です。
内部資源(強み・弱み・機会・脅威)を整理
こうして多面的にデータを重ねることで、性格タイプのバイアスを最小限に抑えながら、より現実的で実行可能な経営プランを描けるようになります。
企業は創業期・成長期・スケール期で必要スキルが変わり、外向型のESTP・ENTJは資金調達や交渉、ENFJ・ESFJはリクルーティングと組織活性、ESTJ・ISTJはガバナンスと内部統制で強みを発揮します。フェーズごとに最適なタイプへハンドルを委ねると、戦略速度と運用精度の両方が高まりやすくなります。
自分のギャップを可視化する手段として、360度フィードバックとボードアセスメントで行動・ハードスキルを数値化し、特定の基準(例:偏差20%超)に基づいて優先改善領域に設定する方法が有効です。さらに業界委員会、アクセラレータ、CEOフォーラムの三層ネットワークで外部知を取り込み、四半期ごとにKPI(資金調達額・採用成功数・NPSなど)をレビューすれば、学習曲線を指数関数的に引き上げながら企業成長を加速できます。
経営者に向いている性格タイプのまとめ

世界的に成功を収めるリーダーに関する多くの研究や調査において、いくつかの核心的特性が繰り返し浮かび上がっています。その代表格がグリット(やり抜く力)、自己効力感(自分ならできるという確信)、学習敏捷性(未知の領域を素早く吸収する柔軟性)です。興味深いのは、これらの特性がMBTIタイプを問わず観測される点です。外向型か内向型か、感覚型か直観型かに関係なく、高い成果を出す人は困難を粘り強く乗り越え、自分の能力を信じ、新しい知識を貪欲に取り込み続けています。
一方で、成功者の強さは順風満帆な時期ではなく逆境でより鮮明になります。ここで鍵を握るのがレジリエンス(回復力)とアダプタビリティ(適応力)です。急激な市場変化に対し、既存戦略を素早く見直し、学んだ教訓を即座に次の行動に反映させることで競争優位を維持できる仕組みが出来上がっています。
これら共通特性は生まれつきだけでなく鍛錬によっても伸ばせます。グリットは長期目標を細分化し、毎週の進捗を可視化することで強化できますし、自己効力感はマイクロゴールを設定して成功体験を積み重ねると高まります。レジリエンス向上には瞑想やリフレーミングを取り入れたメンタルトレーニングが効果的です。また、アダプタビリティ強化にはディシジョンゲーム(複数のシナリオで意思決定をシミュレーションする訓練)が有用で、変化の速い状況下でも冷静に最適解を導き出す習慣が身につきます。これらのメソッドは一日15分程度から始められるため、読者自身のスケジュールに組み込みやすいのも魅力です。
正確なセルフアセスメントには「MBTI結果・360度評価・財務指標」の三つの要素を統合したアプローチが、多角的な視点を提供し、自己理解を深める上で参考になる場合があります。以下に、その一例として6ステップ方式を提案します。
正確なセルフアセスメントのための6ステップ
- MBTIで強み・弱みを整理する
- 360度評価で行動ギャップを可視化する
- キャッシュフローや負債比率を数値化し、リスク許容度を確認する
- 三つのデータを重ねてスキル・行動・資金のボトルネックを特定する
- 改善インパクトとコストをスコアリングし、優先順位を決定する
- 優先項目をKPIと紐づけたアクションリストへ落とし込む
感覚ではなくデータで現状を把握できる点が最大の利点です。
目標設定はSMARTフレームで短期・中期・長期を設計します。短期は「毎週2時間の財務モデリング学習」など具体的タスクに、中期は「年間売上20%増と残業時間月10時間以内」など複合指標に、長期は「海外2カ国展開で営業利益率15%以上」のようにビジョンと数値を両立させます。OKRトラッカーや自動計算シートを併用すると進捗管理の負荷が下がります。
リソース配分では、Toggl Trackで時間を可視化し、Money Forward MEで支出上限を設定し、HabitBullで睡眠や運動をトラッキングすると、時間・資金・エネルギーの最適化が図れます。データをNotionなどに集約してパーソナルダッシュボードを作成すれば、「どこに投資すべきか」が一目でわかります。
行動計画は作成後のイテレーションが鍵です。
この多層レビューを継続することで、環境変化や価値観の変化を逃さず捉え、常に最適化された行動計画を維持できます。

経営コンサルタント
[中小企業診断士] [社会保険労務士]
20年以上にわたり燃料業界を中心とした中小企業のDX推進を支援。
現在は製造業・小売業・サービス業など幅広い分野に対して、
IT活用や業務効率化、経営戦略の策定などを一貫してサポート。
講演やセミナーにも登壇し経営や起業の実践的なアドバイスを得意とする。