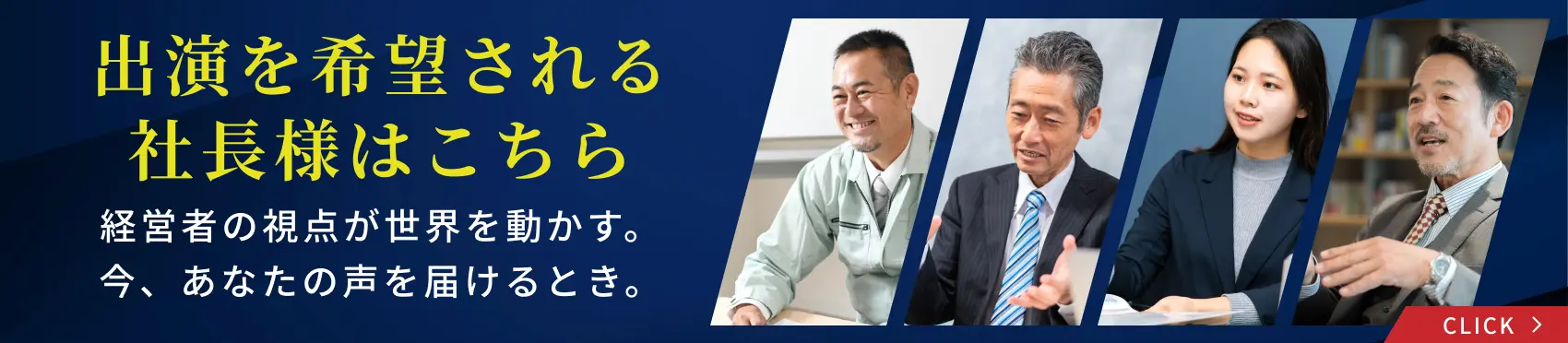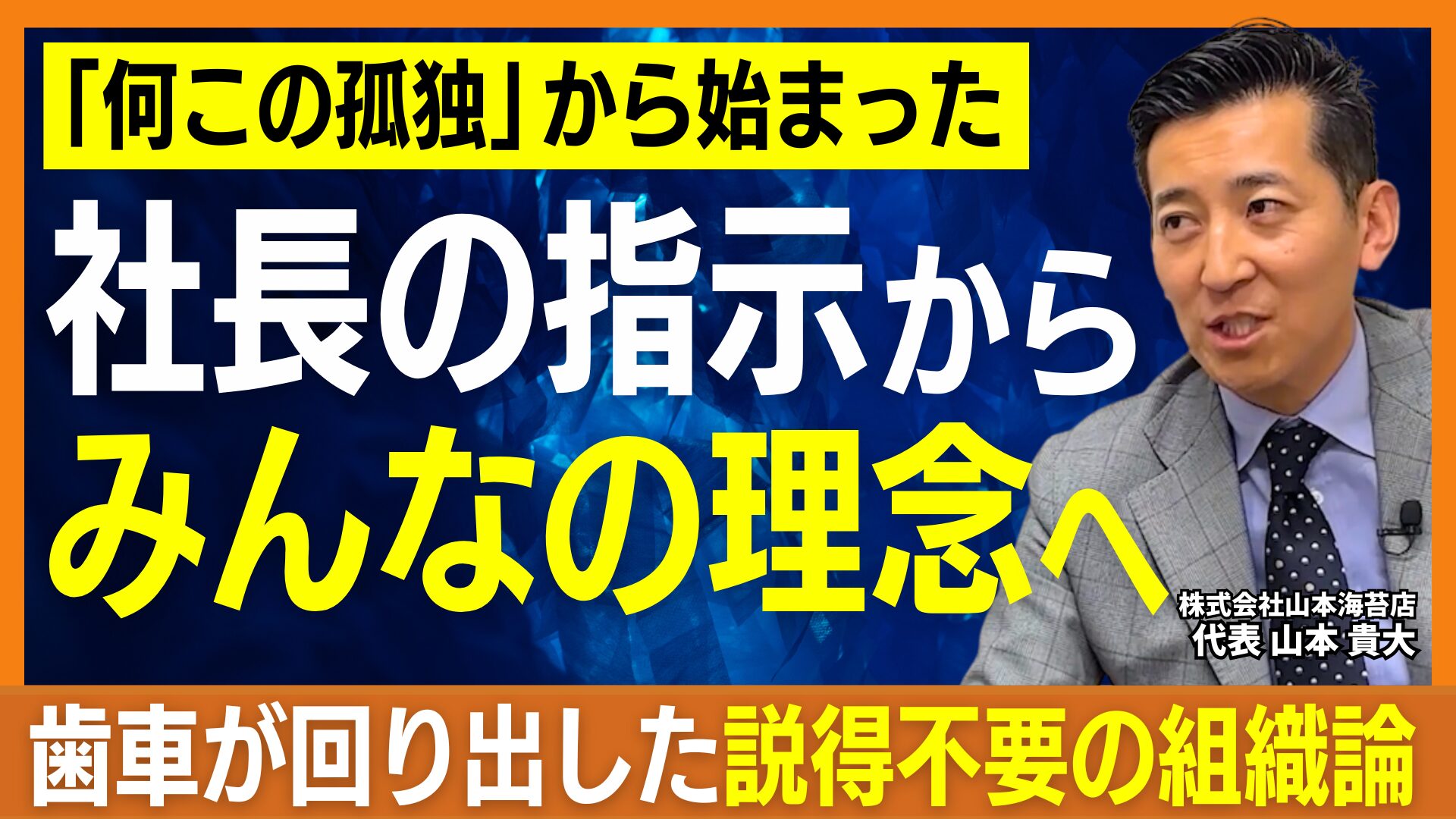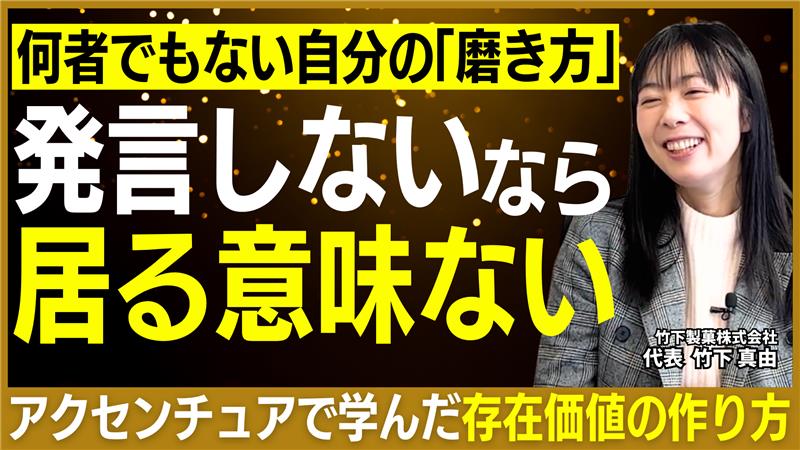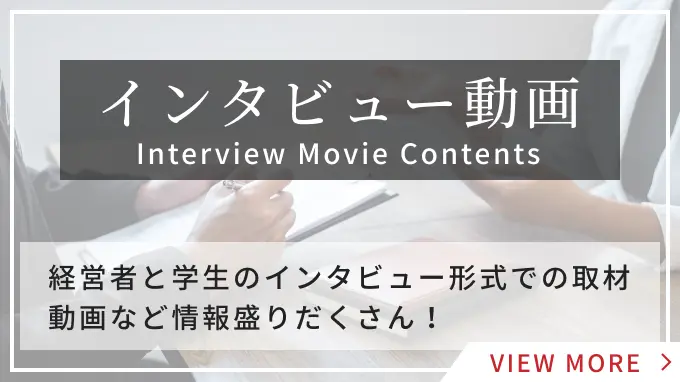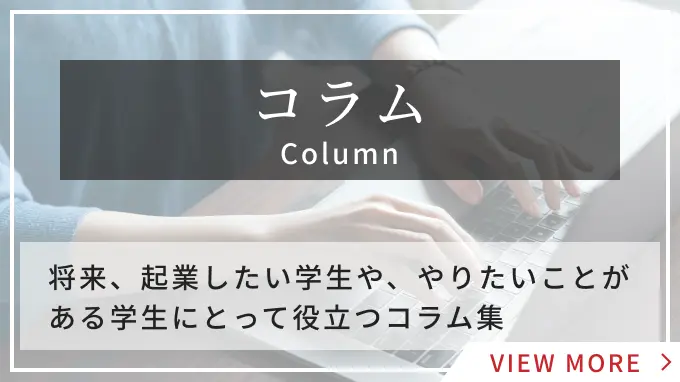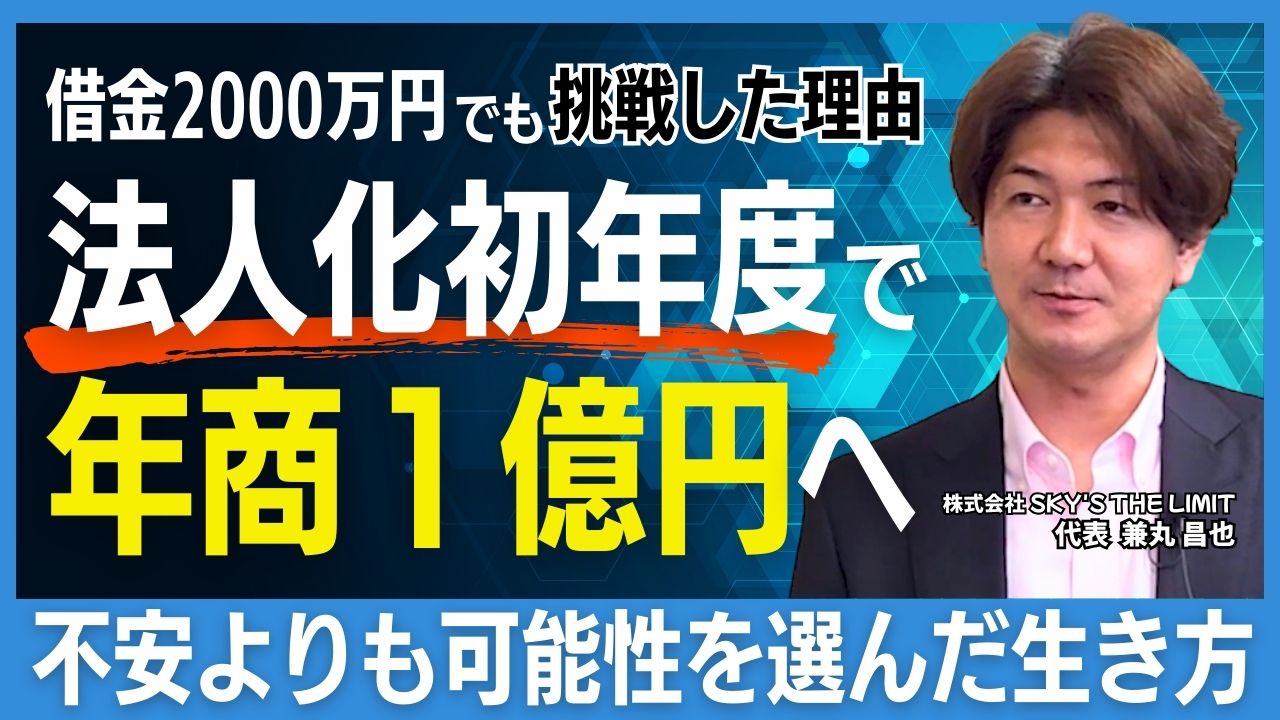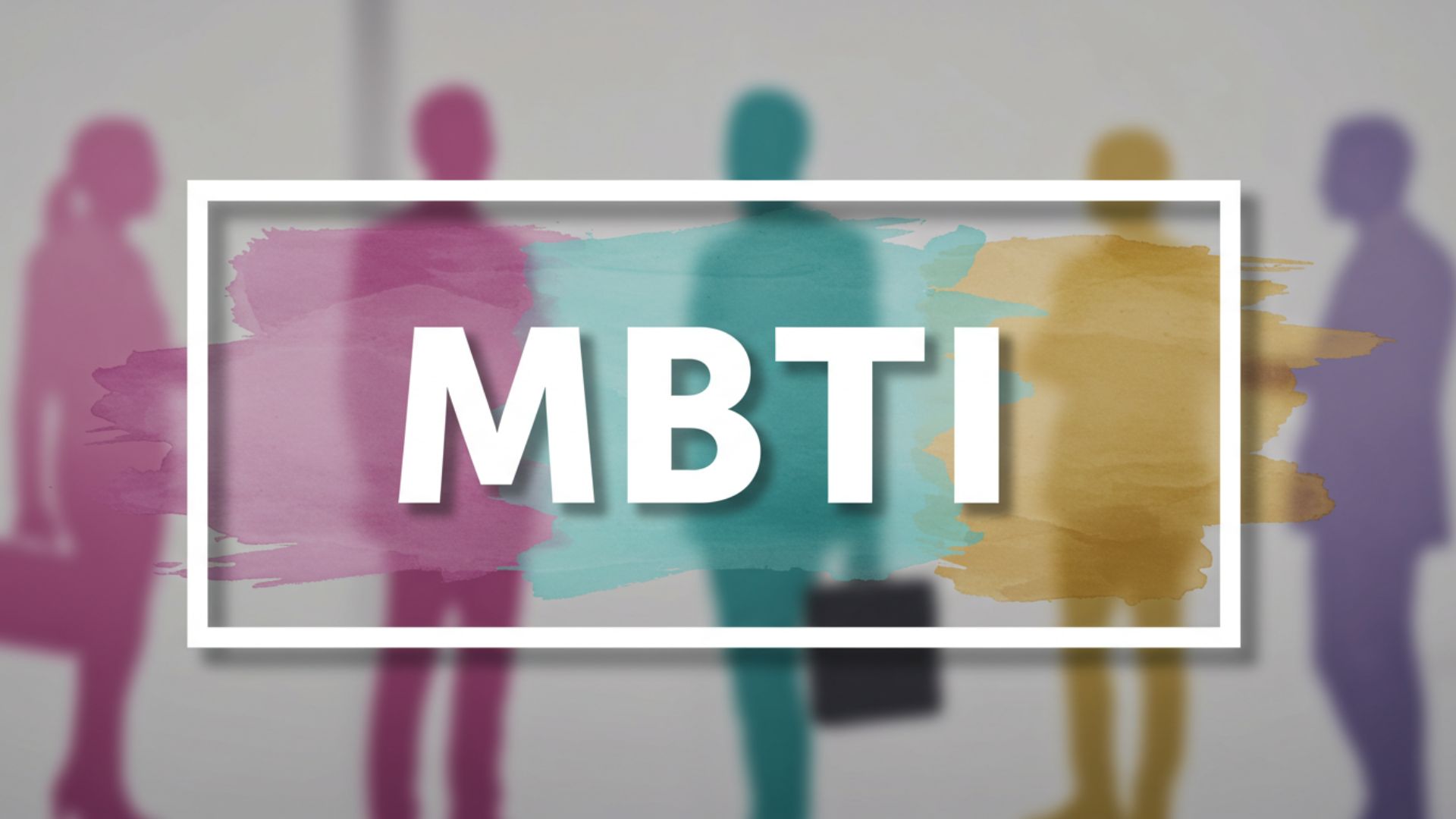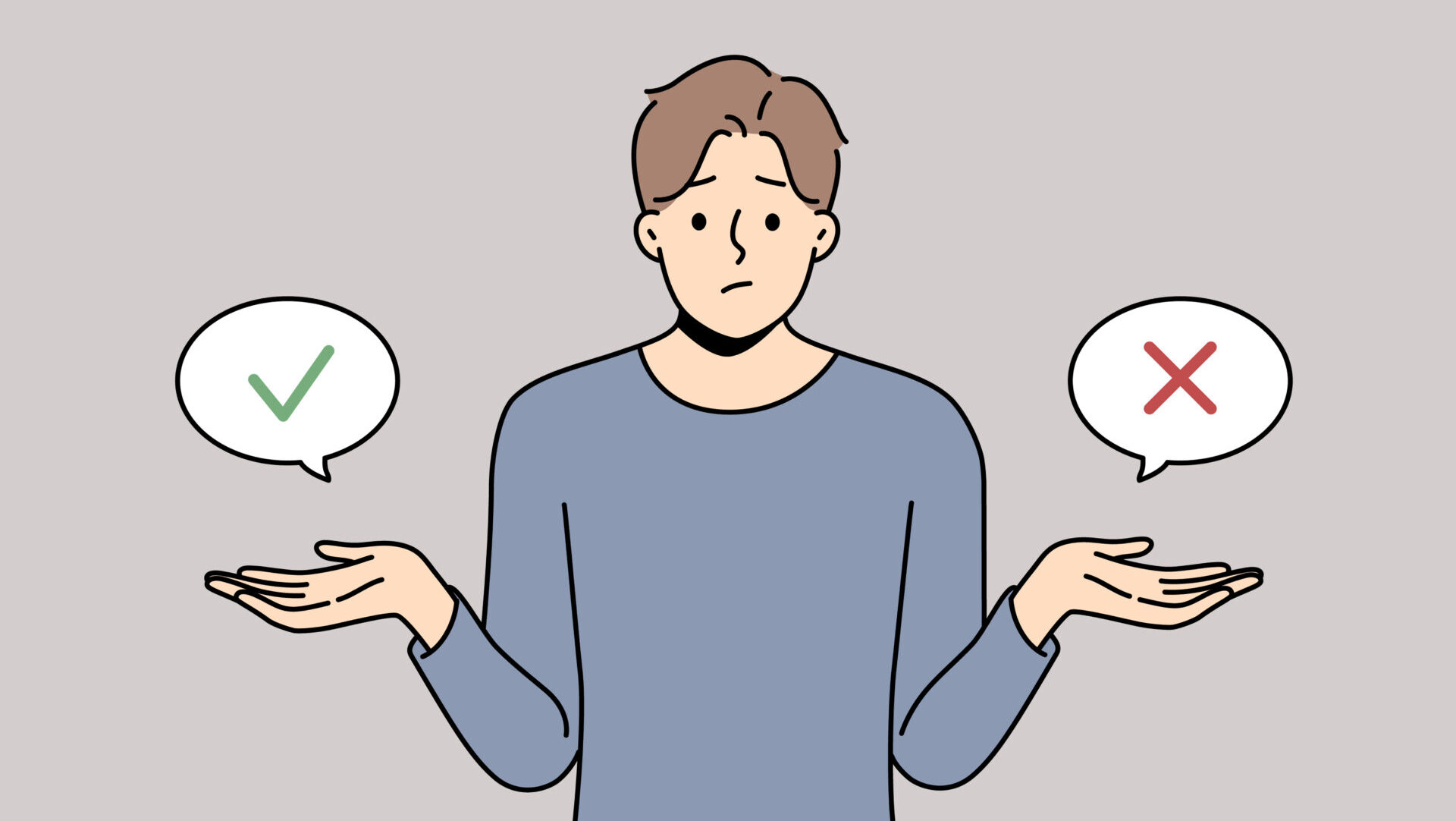健康経営に取り組む企業の実態と課題とは?ワークライフバランスの真実

健康経営という言葉を耳にし、その意味や具体的な取り組みについて知りたいと考えている方もいらっしゃるかもしれません。健康経営は、単なる福利厚生の充実だけではなく、企業の将来性や従業員が働きやすい環境であるかを見極める上で非常に重要な指標となっています。
この記事では、健康経営が何を意味するのか、なぜ現代社会でこれほど注目されているのかを解説します。また、多くの企業が健康経営を推進する中で直面している課題や、公表されている情報と実際の働きやすさとのギャップを見抜くためのポイントもご紹介します。この記事を読み終える頃には、健康経営を本気で実践し、従業員を大切にしている優良企業を見つけるための具体的な視点が得られるでしょう。
目次
健康経営とは何か?その重要性と広がる背景

近年、健康経営という言葉を耳にする機会が増えたと感じるかもしれません。これは単なる福利厚生の充実といった話ではなく、企業が従業員の健康を戦略的に捉え、経営的な視点から実践する取り組みを指します。健康経営は、これからの企業選びにおいて、その企業の将来性や、そこで働く人々の働きがいを判断するための重要な基準となりつつあります。このセクションでは、健康経営の基本的な概念と、それがなぜ現代においてこれほどまでに注目されるようになったのかを深掘りし、皆さんの企業選びの一助となるような情報をお届けします。
健康経営とは、従業員の健康保持・増進を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。この考え方の核心は、従業員の健康を単なるコストではなく、企業の成長を支える経営資源として積極的に捉え、そこに投資していくという点にあります。従業員一人ひとりが心身ともに健康であることは、個人の能力を最大限に引き出し、結果として生産性の向上や新たなイノベーションの創出につながるからです。
具体的には、健康な従業員は集中力が高く、創造的な業務に取り組みやすく、欠勤や休職のリスクも低減します。企業が健康経営に力を入れることは、従業員が長期にわたって安心して働き続けられる環境を整備し、個々のキャリア形成と成長を支援する姿勢の表れと言えるでしょう。このような考え方を持つ企業は、従業員を大切にする文化が根付いている可能性が高いと評価できるでしょう。
健康経営が現代においてこれほどまでに重要視される背景には、日本の社会が抱える構造的な課題が深く関係しています。最も大きな要因の一つは、少子高齢化に伴う労働力人口の減少です。働き手が減少し続ける中で、企業は優秀な人材を確保し、一度採用した従業員には長く健康に活躍してもらうことが不可欠となっています。
また、平均寿命の延伸に伴い、従業員一人ひとりの働く期間も長くなる傾向にあります。このような状況において、従業員の健康を維持し、病気や生活習慣病のリスクを低減することは、企業が将来にわたって持続的に成長していくための重要な経営戦略となります。従業員の健康を守ることは、病気による休職や離職を防ぎ、医療費負担の増加を抑制するなど、経営上のリスクヘッジとしても機能するのです。つまり、健康経営は単なる福利厚生の充実に留まらず、企業の存続と成長を左右する、現代社会において欠かせない取り組みと言えるでしょう。
健康経営に取り組む企業の実態データ

このセクションでは、健康経営に関する客観的なデータをご紹介し、その普及の実態を明らかにします。具体的な数値を用いることで、健康経営への取り組みがどの程度進んでいるのかを概観していきます。
健康経営の実施状況は、企業の規模によって異なる傾向が見られます。一般的に、大企業の方が中小企業と比較して、健康経営に取り組む割合が高いです。複数の調査で、健康経営に取り組む企業の割合は大企業で中小企業を大きく上回る傾向が示されています。例えば、2020年の調査では、健康経営を実践している企業の割合は大企業で52%、中小企業で20%でした。また、2023年の調査では、従業員1,000人超の企業では82.6%が取り組んでいるのに対し、従業員5人以下の企業では40.7%が取り組んでいるという結果が出ています。これは、大企業が健康経営推進のための人員や予算といったリソースを確保しやすいことが 主な要因と考えられます。
しかし、導入率の差がそのまま取り組みの質の差を意味するわけではありません。中小企業の中にも、独自の工夫を凝らして従業員の健康増進に力を入れている企業は数多く存在します。企業を評価する際には、単に企業の規模だけで判断するのではなく、個々の企業がどのような健康経営施策を具体的に行っているかを見極めることが重要です。
経済産業省が推進する健康経営優良法人認定制度への申請企業数や認定企業数は、年々増加の一途をたどっています。この増加傾向は、健康経営への関心が一部の先進的な企業に留まらず、日本企業全体へと広がり、産業界全体でその重要性が認識され始めていることの明確な証拠です。
企業を評価する際、この健康経営優良法人認定制度は、従業員の健康を大切にする働きやすい企業かどうかを判断するための、一つの信頼できる客観的な指標となります。認定を受けている企業は、従業員の健康管理を経営的な視点から戦略的に実践していると評価されており、後のセクションで詳しく説明する「企業を見抜くポイント」の一つとしても参考にできます。
健康経営を成功させるためには、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントが不可欠です。この点において、近年、企業の経営層の意識に大きな変化が見られます。健康経営が単なる福利厚生ではなく、企業戦略の中核として位置付けられるようになったことが明確に示されています。
経営トップが健康経営の最高責任者として積極的に関与することで、健康経営は形式的な制度導入に終わらず、全社的な文化として深く根付いていきます。経営層が健康投資の重要性を理解し、明確なビジョンを持って推進することで、必要なリソースが適切に配分され、従業員一人ひとりの意識改革にもつながります。したがって、企業のウェブサイトや説明会などで、経営トップが健康経営についてどのようなメッセージを発信しているかを確認することは、その企業が健康経営を本気で推進しているかどうかを見極める重要なサインとなります。
多くの企業が直面する健康経営の3つの大きな課題

健康経営は、従業員の健康を経営の重要課題と捉え、戦略的に推進する取り組みです。しかし、多くの企業がその実現に向けて歩みを進める中で、理想と現実の間にさまざまなギャップや課題に直面しています。健康経営は単に制度を導入すれば良いというものではなく、組織全体での深い理解と継続的な努力が求められるため、いくつかの典型的な壁が存在します。ここでは、多くの企業が健康経営の推進過程で直面する主な課題を具体的に解説していきます。
健康経営を推進する上でしばしば見られるのが、経営層の理解不足という課題です。健康経営が単なる福利厚生の拡充と捉えられ、コストとして認識されてしまうと、十分な予算や人員が割り当てられないケースがあります。経営層が健康経営の長期的な投資効果や、企業の持続的成長に不可欠な戦略としての重要性を十分に理解していない場合、表面的な取り組みに終始してしまいがちです。その結果、健康経営の推進は人事部などの特定の担当者に任され、本来の業務に加えて新たな業務が加わることで、担当者の負担が過度に増大してしまいます。専門部署が設置されていない中小企業や、健康経営専任の人員がいない大企業では、この傾向が顕著です。担当者が疲弊し、モチベーションを維持することが難しくなると、健康経営の取り組みそのものが停滞してしまう恐れがあります。「健康経営に取り組んでいる」と謳いながらも、実際には経営層のコミットメントが弱く、担当者任せになっている企業は、公表情報と実態が乖離している「言行一致」のサインと捉えることができるでしょう。
企業が健康増進のための制度や施策を整えても、従業員自身の関心が低かったり、健康に関する知識(健康リテラシー)が不足していたりすると、その効果は十分に発揮されません。例えば、健康診断後の二次検査の受診率が低かったり、せっかく導入された運動プログラムや健康セミナーへの参加者が少なかったりするケースがあります。従業員が自身の健康を他人事と捉え、積極的に健康行動を起こさない限り、企業側の努力だけでは健康経営は絵に描いた餅になってしまいます。
この課題に対し、優良な企業は単に制度を「用意する」だけでなく、従業員の意識改革にも力を入れています。健康診断結果を分かりやすく解説するセミナーを開催したり、ウォーキングイベントなどの参加型プログラムを通じて運動習慣を促進したり、社内報やイントラネットで健康に関する有益な情報を提供したりする工夫が見られます。単発的なイベントではなく、継続的な情報発信や啓発活動を通じて、従業員一人ひとりの健康リテラシーを高め、主体的な健康行動を促している企業こそ、健康経営を深く推進している証拠と言えるでしょう。
健康経営の取り組みを推進する上で、その効果を客観的に測定することの難しさは大きな課題です。健康への投資が、具体的にどの程度の生産性向上や離職率低下、医療費削減に貢献したのかを数値で示すことは容易ではありません。効果が見えにくいと、経営層からの継続的な投資への理解が得られにくくなったり、担当者のモチベーション維持が困難になったりすることがあります。
この課題に対して、先進的な企業は健康管理システムの導入により、従業員の健康診断結果やストレスチェック結果、就業データなどを一元的に管理し、分析を進めています。また、「肥満リスク者の割合を〇%改善する」「特定保健指導の実施率を〇%向上させる」といった具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定し、その進捗を定期的にモニタリングすることで、効果の可視化に努めています。このように、漠然とした目標ではなく、具体的な数値を掲げて計画的に健康経営を推進している企業は、PDCAサイクルを回しながら着実に成果を出そうとしていると判断できます。具体的なKPIが公表されているかどうかも、企業の本気度を見極める重要なポイントになります。
ワークライフバランスの真実|制度と実態のギャップを見極める

企業選びや職場環境を考える上で、ワークライフバランスを重要な要素として挙げる方は多いでしょう。企業が提示する「育児休業制度完備」や「フレックスタイム制度導入」といった情報だけを見て、本当に働きやすい企業なのか判断するのは難しいと感じることもあるでしょう。このセクションでは、企業が公表する制度と、実際に現場で運用されている実態との間に存在するギャップに焦点を当て、真にワークライフバランスを重視する企業を見極めるための視点を提供していきます。
「福利厚生が充実しています」という企業のうたい文句を目にすることは多いですが、その言葉を鵜呑みにして良いのでしょうか。企業で働く人々や、これから企業を選ぶ人々が抱える「公表情報と実態にギャップがあるのではないか」という不安はもっともです。例えば、育児休業制度やフレックスタイム制度が明文化されていても、実際に制度を利用する社員がほとんどいなかったり、「制度はあっても利用しづらい雰囲気がある」といった実態は少なくありません。このような「形骸化した制度」は、表面上は従業員への配慮を示しているように見えても、実質的な働きやすさにはつながっていないのです。
重要なのは、単に制度が存在するかどうかだけでなく、それが従業員によって「気兼ねなく利用できる」環境が整っているかという点です。例えば、育児休業取得実績がゼロに近かったり、周囲の目が気になって有給休暇を消化しづらかったりする企業では、どれだけ素晴らしい制度が用意されていても、その恩恵を従業員が受けられているとは言えません。働きがいのある職場を見極めるためには、企業のウェブサイトや公表資料に書かれている制度の有無だけでなく、多角的な情報源を通じて、制度の利用率や社員のリアルな声といった「実態」を示す情報を積極的に探すことが重要です。
では、名ばかりの制度ではない、従業員が「本当に働きやすい」と感じる環境を創出している企業は、どのような取り組みを行っているのでしょうか。具体的な事例としては、年次有給休暇の取得促進策が挙げられます。単に制度として有給休暇があるだけでなく、計画的な休暇付与を推進したり、半日単位や時間単位での取得を可能にすることで、従業員が自身のライフスタイルに合わせて柔軟に休暇を取得できるように工夫している企業は、働きやすさを真剣に考えていると言えるでしょう。
また、育児休業制度や介護休業制度を充実させるだけでなく、実際に制度を利用する従業員を積極的に支援し、職場の理解を促す文化を醸成している企業も多くあります。さらに、日々の業務における働きやすさにも配慮し、年間を通じてノーネクタイ勤務を推奨したり、夏場にはカジュアルな服装での勤務を許可したりするなど、従業員の心理的な負担を軽減し、多様な働き方を尊重する企業文化を醸成している事例も見られます。これらの取り組みは、単なる制度の整備に留まらず、従業員一人ひとりのライフイベントや価値観に寄り添うことで、真に働きやすい環境を作り出していると言えるでしょう。
【具体例】企業の健康経営への取り組み施策

このセクションでは、企業が従業員の健康をどのように守り、育んでいるのか、具体的な取り組み施策を紹介します。身体的な健康をサポートする施策から、心の健康、つまりメンタルヘルスケアに至るまで、多角的なアプローチに注目してみましょう。
従業員の身体的な健康を維持し、増進することは、健康経営の基盤となります。多くの企業では、生活習慣病の予防や早期発見、感染症対策など、さまざまな側面から従業員の健康をサポートしています。
例えば、生活習慣病の予防策として、定期健康診断の受診結果に基づいたきめ細やかなフォローアップや、食生活・運動習慣改善のための情報提供を積極的に行っています。健康診断で異常が見つかった従業員に対しては、保健師や産業医との面談機会を設け、専門的なアドバイスを受けられるようにしている企業も少なくありません。また、がんの早期発見にも力を入れており、定期健康診断時に各種がん検診を実施したり、希望者にはMRI脳ドック検診などの高度な検査機会を提供したりする企業もあります。これらの取り組みは、従業員が病気を早期に発見し、治療につなげるための重要な支援となります。
さらに、感染症対策として、インフルエンザの流行時期前には、各事業所で予防接種を実施し、従業員の費用負担を軽減しています。禁煙活動の推進も身体的健康を守る上で重要とされており、世界禁煙デーに合わせて禁煙イベントを開催したり、禁煙補助プログラムを提供したりする企業もあります。社内コミュニケーションの活性化と運動習慣の形成を目的としたユニークな取り組みも見られます。スポーツ大会や運動セミナーの開催、レクリエーションイベントを通じて、従業員が楽しみながら健康増進に取り組める機会を提供しています。
| 要素 | 主な施策 | 狙い |
|---|---|---|
| 生活習慣病予防 | 定期健診の個別フォロー/保健師・産業医面談/食事・運動情報提供 | リスク低減と行動変容 |
| 早期発見 | がん検診/MRI脳ドック/再検査~治療連携 | 重症化予防・早期治療 |
| 感染症・禁煙・運動 | 予防接種補助/禁煙イベント・補助/スポーツ大会・運動セミナー | 集団予防と習慣化 |
近年、従業員の心の健康、すなわちメンタルヘルスケアの重要性がますます高まっています。企業は、ストレスチェックの実施やカウンセリング体制の整備など、多岐にわたる取り組みを通じて、従業員の心の健康維持に努めています。
多くの企業では、精神的な不調を未然に防ぐための予防的アプローチとして、全従業員を対象としたストレスチェックを定期的に実施しています。ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判定された従業員には、産業医との面談を積極的に勧め、個別のサポートを提供しています。これにより、早期に問題を特定し、適切な介入を行うことで、メンタルヘルス不調の悪化を防ぐことを目指しています。
また、長時間労働はメンタルヘルス不調の大きな要因となるため、労働時間の適正化も重要な取り組みです。勤務体制の見直しや、長時間労働者に対する産業医面談の実施を通じて、従業員の過重労働を抑制し、ワークライフバランスの実現をサポートしています。これらの取り組みは、単に制度を設けるだけでなく、実際に従業員が心身ともに健康で働き続けられるような環境を整備しようとする企業の強い意志の表れと言えるでしょう。
健康経営に取り組む優良企業を見極めるポイント

企業を評価する際、単に知名度や業績だけでなく、「働きやすさ」や「従業員を大切にする文化」を重視する方が増えています。特に健康経営を実践している企業は、長期的な視点で従業員の成長と幸福を考えていると言えるでしょう。このセクションでは、皆さんが健康経営に取り組む優良企業を自身の力で見極めるための、実践的なチェックポイントをご紹介します。企業の表面的な情報だけでなく、その実態を深く探るための具体的な方法を理解し、企業を多角的に評価する際の判断材料に役立ててください。
企業が健康経営にどれだけ力を入れているかを見抜く最初のステップとして、「健康経営優良法人」の認定有無を確認することから始めましょう。この認定制度は、経済産業省が「従業員の健康増進を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組んでいる法人」を顕彰するもので、その信頼性は非常に高いと言えます。
認定企業は、経済産業省のウェブサイトや「健康経営優良法人」の特設サイトで公開されています。就職を検討している企業がこのリストに含まれているかを確認することで、その企業が健康経営を対外的にアピールできるレベルで実践しているかどうかの一次スクリーニングが可能です。ただし、認定を受けているからといって安心しきらず、これはあくまで入り口として、次のステップでより具体的な取り組み内容を深掘りしていくことが大切です。
「健康経営優良法人」の認定企業であると確認できたら、次にその企業の公式ウェブサイトや採用サイトをじっくりと読み込みましょう。「健康経営」「サステナビリティ」「CSR」といった専門のページやセクションに注目してください。ここで重要なのは、抽象的な理念やスローガンだけでなく、具体的な取り組み内容が詳細に記載されているかどうかです。
例えば、本記事でご紹介したような「健康診断後のフォローアップ体制」「ストレスチェック後の産業医面談」「具体的な運動促進イベントの実施」といった具体的な施策内容が示されているかを確認します。さらに、「肥満リスクの従業員割合を〇%削減する」といったKPI(重要業績評価指標)や目標数値、そして経営トップからのメッセージが掲載されている企業は、健康経営に対する本気度が高いと判断できます。これらの情報から、その企業がどのような課題意識を持ち、具体的な行動として何を行っているのかを把握することで、実効性のある健康経営が行われているかを見極めることができるでしょう。
企業の公表情報と実際の働きやすさとのギャップを見極めるためには、客観的なデータを確認することが非常に有効です。特に注目すべきは、福利厚生制度の利用のしやすさを示すデータです。例えば、「育児休業取得率(男女別)」「有給休暇取得率」「平均残業時間」といった数値は、従業員が実際に制度を利用できているか、ワークライフバランスが保たれているかを測る重要な指標となります。
これらのデータは、企業のサステナビリティレポートや統合報告書、あるいは新卒採用向けのデータブックなどで公開されている場合があります。また、「離職率」も、従業員の満足度や働きがいを示す重要なデータの一つです。もしウェブサイトなどでは見当たらない場合でも、企業説明会や面接の際に、これらの数値について具体的に質問してみるのも良いでしょう。データに基づいた回答が得られるかどうかも、企業の透明性や誠実さを見極める一つの判断材料になります。
まとめ:健康経営は企業と従業員の未来を作る経営戦略

この記事では、健康経営の基本的な考え方から、企業が直面する課題、そして企業が本当に従業員を大切にする実態を見極めるための具体的なポイントまで、幅広くご紹介しました。
健康経営は単なる福利厚生の充実ではなく、少子高齢化が進む現代において、企業が持続的に成長し続けるために不可欠な「経営戦略」です。従業員が心身ともに健康でいることは、生産性の向上、優秀な人材の確保と定着、そして企業のブランドイメージ向上に直結します。経営層がこの重要性を理解し、積極的に推進している企業こそが、将来性のある企業と言えるでしょう。
健康経営を重視する企業は、従業員にとって働きがいのある環境を提供し、長期的な企業価値向上にも貢献します。本記事で得た知識をぜひ活用し、「健康経営優良法人」の認定だけでなく、企業のウェブサイトでの具体的な取り組み内容、福利厚生の利用率や離職率などの客観的データにも着目して、働きやすい企業、あるいは真に従業員を大切にする企業を見極めるための判断材料としてください。皆さんが、より良い選択をするための一助となることを心から願っています。

経営コンサルタント
[中小企業診断士] [社会保険労務士]
20年以上にわたり燃料業界を中心とした中小企業のDX推進を支援。
現在は製造業・小売業・サービス業など幅広い分野に対して、
IT活用や業務効率化、経営戦略の策定などを一貫してサポート。
講演やセミナーにも登壇し経営や起業の実践的なアドバイスを得意とする。
最新記事